|
どうしようもなく胸を苛むのは その思い出があまりにも愛しくて あまりにも現実にそぐわないものだからだろうか……  ⅩⅠ 追憶 瞳のことでからかわれるのは、いつものことだった。 それでも、なかなかそれに慣れられるものではなくて。 闇雲に走って、笑い声から逃げた。 そして気がついたときは、いつも傍にいるはずのが何処にもいなくて。 一人ぼっちの不安も勿論あったのだけれど、母様に心配をかけるということのほうが私には多くて。 見知らぬ場所で、私は途方に暮れていた。 幼いながらに、この瞳が私のコンプレックスだった。 誰もいない路地で、私は泣いていたのかもしれない。 「おい、お前。どうしたんだ?」 かけられた声に、顔を上げることが出来なくて。 気持ちの悪い目だ、って言われる目。 向けたら、せっかく声をかけてくれたその人まで、嫌悪に満ちた目を向けるんじゃないか、なんて。 思ってしまって。 固く目をとじて、下を向いていた。 「おい。話聞いているのか?」 「……うん」 「聞いているなら、ちゃんとこっち見ろよ」 「……やだ」 絶対に、彼を見たくなかった。 みた瞬間に何を言われるか。 もう分かっていたから。 この瞳は、父様の遺伝。父様が私たち兄妹にくれた唯一のものが、この瞳だった。 ……いらないのに。 母様は綺麗な瞳と言ってくれるけれど。 ……嫌い、だった。 こんな瞳、大嫌い。 「こっち向けって言ってるだろう!」 「向いたらあんた、私のこと、気持ち悪いって言うに決まってる」 「何でだ?」 「何でって……この目だから」 言って、私は漸く彼の方を見た。 そこに立っていたのは、綺麗な少年。 プラチナの髪と、アイスブルーの瞳。 幼い私が見ても、文句なしに綺麗なその人は、自分とはあまりにも違いすぎて。 不公平だ、なんて思った。 その人は一瞬、目を大きく見開いて。 この反応も、いつものことだから。 傷つくことなんて、ないはずなんだけど。 やっぱり、慣れられなくて。 こんな綺麗な人からも、嫌悪の眼差しを向けられるのかと思うと、本当に辛くて。 どうして私、こんな容姿なんだろう。 人為的に、遺伝子に操作を加えた筈なのに。 項垂れる私に、彼は怒ったように真っ赤になって。 「お前何で、そんなに嫌がるんだ?」 「気持ち悪いって、言われるから」 いつも言われていること。 でもだからといって、傷が癒えるわけでも傷つかなくなるわけでもなくて。 自分で言った言葉に傷ついている、幼くも愚かな私。 「綺麗な瞳じゃないか」 「……え?」 「お前の目、すごく綺麗だ。夕焼けよりも、ずっと綺麗じゃないか」 綺麗……? 嫌悪の対象でしかなかった瞳。 それを、綺麗と言ってくれたことが単純に嬉しくて。 私は、笑っていた。 彼も、笑って。 幼い子供二人、ほのぼのと。 「俺は、いざーくだ。お前は?」 「私は……」 彼が名乗って、私も名前を言おうとしたのだけれど。 丁度彼を探しに来た家の人に、それは遮られて。 多分、その人にはわかったのだろう。 私が、彼とつりあう身分の人間ではない、と。 ……無理もない話。 私が着ていた服は、からかわれて泥をぶつけられたせいもあるけど、酷いものだったから。 嫌悪たっぷりの目で、見下すような目で見られた。 彼は、そんなことには頓着した様子もなくて。 「名前は?」 「イザーク様っ!」 「おうちの人に怒られるよ。だから、じゃあね」 手を振ると、彼は迎えに来た人の手を振り切って。 大きな声で叫んだから。 「また会えるかっ!?」 びっくりしたけど嬉しかったから。 私も、また会いたいと思ったから。 だから、頷いた。 幸せな、幸せな思い出……。 幸せすぎて、この手で引き千切ってしまいたいほどの……。 目が、覚めた。 見知らぬ天井が、広がっている。 現状を把握しきれなくて、私は軽く頭を振った。 ……頭が、痛い。 躯をおこすと、ベッドサイドのテーブルにミネラルウォーターのペットボトルと紙コップが置いてある。 ペットボトルを重石にするようにして、その下にはメモが挟まっていた。 『喉が渇いたら、飲めよ』 書かれた文字は、間違いようもなくミゲル先輩のものだった。 けれど、部屋の主の姿はなくて。 「先輩?」 呼びかけても、答えはない。 声を出すと、急に喉の渇きを実感して。 行儀は悪いけれど、先輩の好意に甘えることにして、ペットボトルに手を伸ばした。 紙コップに中身を注いで、口をつける。 喉にその微かな冷たさが、染みた。 「おっ、。目が覚めたか?」 「先輩、私……」 「話は後々。ホラ、飯」 先輩が言って、トレイを差し出す。 今日のメニューを思い出して、胃がむかむかしてきた。 今日のメニューは確か、ハンバーグ。 戦時下の前線で贅沢を言うつもりはないけれど、食べたくない。 「……食べたくないです」 「ダメだ、。ただでさえそんなに細っこいのに、食わなきゃ躯もたねぇぞ」 厳しい顔で先輩が言って、頷く。 ……そう、私は軍人だ。躯が資本。分かりきっていること。 無理にでも、食べなくては。 「え……?」 トレイを受け取って、思わず絶句した。 今日のメニューは確かに、ハンバーグだった筈だ。 ベッドサイドの椅子に腰欠けた先輩のトレイには、確かにハンバーグが載っている。 でも、私のトレイにあったのは……。 ほかほかと湯気を立てる、卵粥だった。 他にも人参や玉葱、葱なんかが入っていて、すごく美味しそうな……。 隣には、なぜか知らないけどウサギリンゴの姿まであって。 「先輩、これは……?」 「ミゲル先輩作、=嬢への本日の夕食。あ、味見はちゃんとしてるし、妙なものは入れてないから。安心して食えよ」 「いや、そうでなくて。……先輩が作った?」 一瞬、頭がフリーズした。 私は、先輩に食事まで作らせたのか……? 「何?食いたくない?」 「いえ、いただきます」 「そうそう。人間素直が一番だぜ、」 にっこり笑って、先輩も自分の分の夕食の攻略にかかった。 添えられているスプーンを手に、粥を掬い取る。 とろりとしていて、本当に美味しそう……。 別に猫舌なわけではないけれど、熱いものは少し苦手だから、ふぅふぅと息を吹きかけて口に運ぶ。 「ん?どうだ?味は」 先輩が言って、顔を覗き込む。 そして、ぎょっとしたように 「ど……どうしたんだ、。何か、嫌いなものでも入ってたか?不味い……か?」 問われて、ふるふると首を横に振る。 頬に伝わる温かいものに、涙が零れていることを悟った。 美味しかった、から。 あったかくて、先輩の温かさが伝わって、だから溢れた涙だから。 「美味しい、です……」 「お、そうか。それは良かった」 満足そうに微笑むミゲル先輩は、本当に優しくて。 ほんの少し顔の筋肉を動かして、笑えるように努める。 本当に感謝している、と。言葉ではなく態度で伝えるために。 「飯、食いたくないかなと思ったんだ。今日、ハンバーグだったし」 「はい。今日はちょっと、ハンバーグは……」 「だろ?だから…… 厨房の奴ら脅して作らせて貰った」 「脅しっ!?」 えへっ。なんて。可愛らしい仕種で言う先輩。 ……二十歳過ぎた男がそんな仕種をしても……。 ……可愛いけど。 でも、可愛いと素直に認めるには難のありすぎる台詞を先輩は口にして。 思わず……吹き出してしまったんだ。 「厨房の皆さん、ご協力有難う。お前らの尊い犠牲は、決して忘れねぇから」 「……なんて言って脅したんですか?」 「別に大したことは言ってないぜ?」 先輩の台詞に、一瞬胸を撫で下ろしたのだけれど。 次の瞬間、先輩は息も止まるほどに綺麗に微笑んで。 「え?俺の好きにさせなかったら、次の戦闘の時、間違って敵じゃなく味方に攻撃しちまうかも、って」 「っっっ――!?」 「いやぁ、俺は冗談だったんだけどねぇ」 ……それの何処が、『大したことない』んだろう……? て言うか、冗談じゃ済まされないだろう、それは。 私は、思わず厨房の面々に同情したい気持ちでいっぱいになった。 こうなったら、こうして先輩が作ってくれた手料理は責任を持って綺麗に食べなくては。 犠牲になったみんなに申し訳がない。 いや、死んではいないけど。気分的に、な。 黙って黙々と食べ続ける私に、先輩は小さく笑って。 「嫌なことは、さっさと忘れちまえ」 「先輩……」 「ここは戦場だ。些細な迷いが、命取りになる。実戦経験のあるお前なら分かるだろ?=」 「はい……」 厳しい、口調。 厳しいんだけど、でも静かで、優しくて。 『兄』が『妹』を教え諭すときは、こんな口調なのかもしれない。 「迷うな。忘れろとは言わないし、許せとも言わない。でも、迷うな。戦場では」 「分かってます」 「死に場所を求めるようなことはするな。勿体無いだろ。そんな生き方は」 「はい……」 「死ななきゃ手に入らない自由なら、自分を束縛するものなんて捨てちまえ。お前は、お前だ。お前は、『=』という名の、一人の人間なんだ。お前の価値は、おまえ自身が決めろ。命を捨てることは、自分を捨てることだ。……それは、自由なんかじゃない。ただの逃避だ」 私が自ら、命を捨てようとしたこと。 それを、諫めてくれている人が、いて。 お説教してくれて。 それって、ねぇ。。それって、堪らなく幸せなことだね……? 「っ!!」 「……アスラン?」 「自殺しようとしたって、本当かっ!?なんて馬鹿なことを……!」 飛び込んできたアスランに、目を丸くする。 ……心配してくれるのは有難いが、アスラン。人の部屋に無断で入るのはやめたほうがいいと思うぞ? また、ハロの特殊機能を使ったのか? 「聞いているのか、!?」 「……聞いている。心配かけてすまない」 「本当に、僕たち心配したんですよ。さん」 「そうそ。ダメだよ、。仲間が死ぬなんて、俺嫌だよ」 「ニコル……ラスティ……」 胸が、いっぱいになる。 優しい人たち。 涙が出るほど、優しくて愛しい人たち。 ……昔会った時は、イザークもそうだった。 「またね」って、約束したのに……。 でも、あれから一度も会えなかった。 悲しくて、でも、いつか会えると思ってた。 どうして再会が、あんな形だったんだろう。 どうして、貴方は私を忘れているんだろう。 傷ついている私が、優しい貴方を期待していた私が、ひょっとしてただの愚か者だったのだろうか。 どうして私は、貴方を嫌えない?憎めない? イザークよりも、アスランや先輩のほうが優しいのに。 でも私にとって、アスランは『弟』。先輩は『お兄さん』。そうとしか認識できない。 一番の歪みは、これ? 先輩を……アスランを、そういう対象に見ることが出来れば、よかったのにね……。 嫌えない私が、一番の愚か者。 本当に、愚か者だ……。 あの日、イザークの手を取れば良かったんだ。 差し伸ばしてくれた手を、取ればよかった。 後悔は、してもし足りない。 「ミゲルってば、イザークを殴ったんだよ。」 「え……?」 考え事に没頭していた私の耳に、突然入ってきた言葉。 思わず聞き返すと、ラスティは同じことを繰り返す。 先輩は苦笑しているけど、それって……それって、大変なことじゃないのか? イザークの母親は、エザリア=ジュール。 国防委員会きってのやり手と評判で、イザークはその愛息子で。 ザフトを統括するのは、評議会の中の国防委員会だ。 そんなことをして……。 「気にすんな、」 「だって、先輩。それって……」 「気にすんな」 「だって、私のせいで、先輩……」 「お前のせいじゃない。俺が許せなかったんだ。同じ男として。それだけのことなんだ。……ったく、ラスティも。どうせならもう少し、別のことを言えよ。アスランがイザークに殴りかかった、とかよ」 先輩は、そういうけど。 でも……。 そんな簡単なことには、思えない。それで済むとは、思えないんだ。 アスランならば、問題ない。 アスランは、評議会の実力者であるパトリック小父様の息子だから。 たとえエザリア=ジュールと雖も手出しは出来ない。 でも、先輩は違う。 話にみんなが夢中になっている、その隙を見計らって、そっと部屋を出た。 目指すのは、イザークの部屋……イザークと、私の部屋。 暗証番号を入力すると、扉が微かな音を立ててスライドする。 「なんだ。貴様か」 面白くもなさそうに、イザークが言って。 でも私は、イザークの顔に目が釘付けになる。 痛々しいくらいに、腫れた顔。 青黒い鬱血。 イザークのほうが私に、酷いことをしたのに……。 「話がある」 「俺にはない」 「私には、あるんだ……!」 声を荒げると、驚いた顔をしてイザークが私を見下ろした。 腕を組んだままの、傲慢な態度は崩さないまま。 「……なんだ?」 「それは、先輩……ミゲル先輩が……?」 「緑に傷を負わされたのか、と笑いに来たのか?」 「違う!」 アイスブルーの瞳は、冷たくて。 萎縮してしまいそうに、なる。 「先輩に、何もしないで欲しい」 「あぁ?」 「お願いだから……頼むから、先輩に何もしないで……!!エザリア様に、国防委員会に報告しないで欲しい……お願いだから!」 先輩に……何もしないで。 いくらザフトに階級がなかろうが、赤は緑より格上。 格下のものがこんなにも殴って、それで何もなしになる筈がない。 「別に、母上に報告するつもりはない」 「本当……に?」 「ああ。……貴様が土下座して頼むならな」 土下座……?イザークは、私のプライドを粉々にしなければ気が済まないらしい。 でも……でもそれで、先輩の命が……無事が買えるなら、安いものだ。 意を決して、重力下の床に膝をつく。 床に額がつくぐらい、頭を下げて。 「お願い……します。エザリア様に報告しないで……ください」 イザークが息を呑んだのが、雰囲気で分かった。 意外……か?私が他者に膝を屈することが。 そうだな。普段の私なら、絶対にこんなことしないだろう。 でも、先輩のためだから。 先輩のためなら、これくらい安いものだ。 「そんなに、貴様は……」 「え……?」 「もう、いいっ!」 イザークに腕を掴まれて、躯を引き起こされる。 その仕種に、優しさの欠片もないのに。 振り仰いだイザークの顔が、悲しみを堪えているようにも見えて。 思わず、遠い昔の彼と重なった――……。 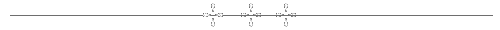 BGMはT.M.Rで『hear』と『翳り』で。 え?古い? いいじゃないですか。私的にこの二曲は想像力喚起してくれます。 基本的に小説書くときに音はかけないのですが。 それにあまり、『恋哀歌』は曲かけて書かないなぁ。イメージソングもない気が……。 『Zips』聞きながら『恋哀歌』書いたこともあるし。 ちなみに。『鋼のヴァルキュリア』は『Meteor』です。 でもこの曲、聞きながら涙でそうになるんですよね。 困ったもんです。 なんか今回、イザークがかなり……うちの彼はやっぱりSでしょうかね。 ここまで読んでいただき、有難うございました。 |