|
愛しているから、貴方の側を望まない。 結婚なんて、死んでも嫌。 貴方だって、そうでしょう? 私と結婚なんて、嫌でしょう? なのに何故、断ってくれなかった?  Ⅲ 婚約通達 いつかは来るものと、覚悟はしていた。 私が女であると、隊長が隊員全てに明かす日。 それが、出来るだけ遠い未来であればと願っていたのは、ただ私が臆病だからなのだろう。 アイツが私を蔑む目で見るのが、分かるから。 ただ、その時私の隣にはきっと、アスランがいてくれるのだろう、と。 それだけは、疑いもせずに思っていた。 アスラン……私の大切な、幼馴染。 隊長に言われ、赤の女性用軍服に袖を通す。 女性用といわれても、男性用とたいして変わらない。 上着の丈が短くなり、ズボンの代わりに膝丈のタイトスカート。そして、白いショートブーツ。 後頭部で束ねていた髪を下ろすと、やっぱり女にしか見えなくて。 いくら願おうと、生まれもった性別は変えられないものだとぼんやりと思った。 久しぶりのスカートに、足元がスースーするのを感じる。 ……動きにくい。 こんな格好、本当に久しぶりなんだな、と。元々女である筈なのに女装しているような気分になる自分に、苦笑した。 「うわぁ。 のスカート姿、久しぶり」 「アスラン……私も、女装しているような気分になって少し困っていたところだ」 「女装って、 ……。面白いことを言うね。 は元々女の子じゃないか」 少々セクハラ発言な気がしないでもないアスランの発言に、苦笑いしながら答えると、さもおかしいと言いたげにアスランは言葉を繋いだ。 今日から、ザフトにもプラントにも、『 = 』は事実上存在しなくなる。 私は、戻るのだ。 『 = 』から、『 = 』へ……。 「そうだ、 。隊長がお呼びだ。ミーティング、開始するそうだよ」 「ああ、いよいよか。……側に、いてくれるか?アスラン」 「勿論だよ、 」 年上なのに、年下のアスランに頼る自分が滑稽だと、心の中で思いながら。 アスランの優しさに甘えてはいけないと言うことくらい分かりきっているのに、甘えてしまう弱い弱い私。 「……イザークは、知ってるのか?その…… のこと……」 「さぁ、どうだろう。……まぁ、知っていようがいまいが、侮蔑の目で見られることだけは確かだな」 それを思うと、今から気が重い。 あの子に…… に見せていた、あの優しい笑顔なんて見せてくれなくてもいいから、もう少しだけ、優しくして欲しい。 そう願ってしまう私は、本当にイザークが好きなんだな、と自嘲気味に思った。 こんな辛いだけの恋なんて、いっそ捨ててしまいたかったのに。 だから私は、必要以上に『軍人である私』に拘っていたのかもしれない。 私は、アイツを癒してあげることなんて出来ない。 戦時中の軍人である、と言うこと。そしてゆくゆくはジュール家を、プラントの未来を背負って立つ、ということ。 並ならぬ負荷を、既に十分以上に与えられているアイツを、私は癒してやることはできない。 私は、『包容力ある優しい妻』にはなれないだろう。 女らしいことだって、何一つ出来ないのが現実だ。 まぁ、家事一般は出来るか、一応。……殺風景な性格だが。 ああ、本当に目に浮かぶようだ。冷め切った夫婦にしかなれないだろう、私たちの姿が。 「さて、何日もつだろうな。『婚約者』と言う関係は」 「何日って……」 「そうもつまい。いずれ……一週間もしないうちに婚約破棄しているかもしれないぞ?」 ああ、本当に有得そうだ。 その時は、せいぜい婚姻統制下に咲いた悲劇の恋として持ち上げられるのだろう。 イザーク=ジュールと故=嬢の悲恋。ああ、案外いいタイトルかもしれない。 役に立たなくなった私を、今度こそ父上は見捨てるかもしれないが、それもいい。 それは私に、なんらマイナスに働くものではないのだから。 「俺との遺伝子の適性率が高ければよかったのに」 「アスラン」 「そうしたらさ、父上は絶対に、を俺の伴侶に決めたよ。父上、を可愛がっていたから」 「そんなことを言ってはいけない、アスラン。アスランには、ラクス嬢がいるだろう?」 失敗した。 アスランに言わせてはいけない言葉を、アスランの口から言わせてしまった。 アスランには、ラクス=クラインという婚約者が、いるのに……。 ラクス=クライン。プラント全土に遍くその名を知られる、歌姫。 可愛らしい女性だと、思う。アスランにお似合いだ、とも。 ただ、アスランには不慣れな世界にいる女性だから、アスランは少々、二の足を踏んでいるのかもしれない。 けれど、アスラン。 私はアスランに、幸せになって欲しい。 不自然な結びつきを余儀なくされる二世代目同士だからこそ、幸せな結婚をする一対がいてもいいと思う。 そしてそれは、アスランたち二人だろう。 ラクス嬢はアスランに、恋をしている。 アスランさえラクス嬢を愛せば、相思相愛の一対が誕生する。 『愛される』という幸福を、アスランは得ることが出来るだろう。 それが、私の救い。 「俺はに、幸せになって欲しいのに」 「……幸せだ、十分。がいて、母上がいて……二人は今はもう亡いが、今はアスランがいる。これ以上の幸せなど、望まないさ」 「……望んでよ、。は、幸せにならなきゃ」 悲しそうに微笑むアスランに、私はそんなに不幸に見えるだろうか、と思わずそう思った。 ……見えるのだろう。 いや、男と偽って軍に入りMSを操縦している時点で、アスランにとって私は『不幸』に見えるのかもしれない。 「知っているか?アスラン。籠の鳥は自由を渇望する」 「……?」 「私にとって自由は、私の死でしか得られない。……そういうことだ。私にとって何よりも渇望するのは、自由。得るためには、私の命は足枷でしかない」 この命潰えるなら、私はきっと、さぞかし満面の笑みを浮かべていることだろう。 ……と同じだ。 事故死したの遺体は、酷いものだった。 身体の損傷は凄まじく、思わず目を覆いたくなるほどの惨たらしい遺体だった。 しかし、何故か顔だけは、綺麗なままだったのだ。 何の損傷もなく、生前の……一対の双子と称され続けた瓜二つの顔だけは、何の傷もなかった。 その口元には、笑みさえ浮かべていた。 ああ、は漸く解放されたのだ。 その身を戒めてやまない楔から。 「おめでとう」と言って私は泣いた。 嬉しくて堪らないのに涙が出て、悲しくて堪らないのに笑顔を浮かべて。 死は、解放なのだ。少なくとも私とにとっては。 「さて、長々と愚痴に付き合わせてしまってすまなかったな、アスラン。そろそろ時間だろう?」 「ああ。……気にするな、。俺でよかったら、いつでも話を聞くから。それぐらい、俺にさせて?」 「有難う、アスラン」 「のこと、誰にも何も言わせない。だって、は頑張ってきたじゃないか。女の子なのに、俺たちと同じメニューを、ずっとこなしてきたじゃないか」 褒められるのがくすぐったくて、でもアスランにそういわれるのは決して、嫌いじゃなくて。 少しだけ、気持ちが奮い立つような気がした。 「アスランとさん、遅いですね」 ニコルの言葉に、俺は僅かに顔を上げた。 ……=。俺の婚約者殿。 不愉快なだけの存在。 が死んで、それで代わりに宛がわれた婚約者。 はっきりいおう。俺はアイツが嫌いだ。 あの醒めた目も、ぶっきらぼうな言葉も、全てが癪に触る。 腹違いの姉妹だというが、アレの妹のとは大違いだ。 先日、急に実家に帰るよういわれて、俺は母上から俺の婚約が決定したと聞かされた。 当然、俺に拒否権はない。 相手の名は、=。=の腹違いの姉。同僚である=の双子の妹。 から、自分に姉などいないと言われていた俺は、それを言われたとき、ご冗談でしょう、と思わず母上に言っていた。 答えは、実に明快だった。 =は実は女で、彼が=なのだ、と。 あんな男みたいな女、ジュール家に、何よりも俺に相応しくない。 拒否できるものなら、俺だって最初から断っているさ。 だが、現実問題ジュール家には家の助力が必要だ。 意に沿わない婚約。 もっとも、唯一一緒にいたいと願った女性を喪った今となっては、誰と結婚しようが構わない。 例えそれがどれだけいけ好かない女だろうが、甘んじて受けてやるさ。愛などなくても、結婚は出来るのだから。 やがて、扉が開いた。 アスランが、そしてあの女が、戸口で敬礼する。 既に室内にいた隊の面々が、一斉にどよめいた。 「アスラン=ザラ、入ります」 「=、入ります」 「話は聞いているよ……いや」 「はっ。ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ありません」 恐縮そうに頭を下げるのは、確かに……――否、もうか――だった。 その身に纏うは、女性用の「赤」の軍服。 を護るかのように、アスランがその前に立ちふさがっている。 まるで忠犬のようなアスランに鼻で笑うと、俺は戸口のほうへ我が婚約者殿を出迎えに参じた。 慇懃に手を差し伸べると、竦んだように俺を見上げてくる、血の色をした瞳とぶつかった。 ……なんて気持ちの悪い目だろう。 冷たく顎をしゃくると、意味を了解したのか、が俺の手の中に彼女の手を滑り込ませてくる。 ……人前でなければ、誰がこんなことをするか。 唇を噛み締めて、俺に歩調を合わせて歩くと、俺を睨みつけるアスラン。 そんな俺たちに、隊長が揶揄するように呟かれた。 「そんなに婚約者の登場を待ちかねていたのかね、イザーク?」 答えは、決まっている。 心なんて、必要ないのだから。 「ええ、そのとおりです隊長。は私の大切な……大切な婚約者ですから」 の、その強張ったその表情に、例えようもないほどの愉悦を、その時俺は感じた。 この女など、所詮ただの代用品。 出来損ないの粗悪品。ただの、の模造品なのだから――……。 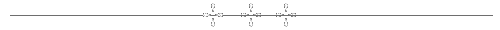 ご……ゴメンなさい!申し訳ありません!すみません!! 予想に違わず酷い男になってしまいました、王子! 粗……粗悪品に模造品はないだろうと思うのですが……手が勝手に文字を打っていました。 あわわわわ。 と……とりあえず、こんな話です。 こんな小説をここまで読んでくださり、本当に有難うございました。 |