|
貴方の言葉は、いつも痛くて。 貴方のその視線を浴びるたびに、思い知らされる現実に、心は麻痺してしまいそう。 お願いだから、これ以上私を傷つけないで……。  Ⅶ プライド 「おはよう、 。隣いい?」 「勿論だ、アスラン」 「昨日はよく眠れた?」 「……ミゲル先輩たちと、酒盛りになった」 私の言葉に、アスランは苦笑いを浮かべる。 その様子を見ると、どうやら彼も餌食になったことがあるらしい。 「お疲れ様」 「いや、酒は好きだから。……ただ酒だったし」 「あはは。面白いね、 は」 私の返答に、アスランは声を立てて笑った。 ……珍しい。そう思わずにはいられない。 再会し、軍属になったアスランは……アスラン=ザラは、表情をあまり崩さなくなった。 いつも、見事なポーカーフェイスで。感情すらも操作しているように見える。 それは、一般の十六歳の少年とはあまりにもかけ離れていて、見ていて痛々しさすら感じてしまうのだ。 「うぃーっす、 。二日酔いはどうだ?」 「全然ありませんよ。先輩こそ、大丈夫ですか?」 「……頭痛ぇ」 「……呑み過ぎだな、ミゲル」 「うるせぇ」 アスランの容赦ない突っ込みに、先輩が毒づく。 アスラン。いくら事実だからといって……いや、事実だから余計に、先輩の機嫌は悪くなると思うぞ? でも、そんなアスランの様子を見れることは、嬉しいことだから。 ごく普通の、ありふれた十六歳の姿。そんなの、滅多に見られるものじゃない。 「全然全く酒の呑めないお子ちゃまはすっこんでろ」 「呑めたからって、別にいいことはないだろう。二日酔いまであるんじゃ、百害あって一利なしだ」 「一利どころか、利益はちゃんとあるぜ?」 「なんだよ?」 アスラン、アスラン。喧嘩腰になっているぞ? 全く。先輩の前では、十六歳の少年に戻るんだな、お前は。 「 と酒が呑める!」 「……はぁ!?」 「た……確かに……!!」 「……」 ミゲル先輩の返答に、私は目を丸くした。 アスランは、悔しそうにしているが……私と酒が呑めて、それでどうした? 特に何も、いいことはないと思うが……。 「私と酒を呑んでも、別にいいことなんてないぞ?」 「分かってないな、 は。 と酒が呑めることが、いいことなんだ」 私の反応に、ミゲル先輩がそういうが……何のことだかさっぱり分からない。 私と酒を呑んで、それがどう『いいこと』に直結するというんだ? 「つまりね、 。皆、君が好きってこと」 「ま、そういうこった。 が好きだから、 と酒呑んだりゲームしたりするのが、嬉しくて仕方がねぇんだよ」 私が、好き……? 私と一緒にいると……私と何かをすると、嬉しい……? どうしてだろう。鼻の奥がつーんと熱くなった。 何か、熱いものがこみ上げてくる。 私は『 = 』として彼らの心のどこかに存在している、と。 そんな幸せな感触に、胸が熱くなった。 「皆、 を大事に思ってるよ」 「お前が『女だから』じゃない。お前が、『 だから』だ」 ミゲル先輩が優しく言って、頭をぽんぽんと撫でてくれた。 優しい優しい……掌の温もり。 焦がれてやまない、人の温もりが、嬉しくて。 込み上げてくる熱いものをごまかそうと、下を向いた。 嬉しかった。本当に嬉しくて、そして哀しかった。 嬉しいのは、誰かが私を認めてくれているという事実。 私自身が大切に思っている人が、私を大切に思ってくれいているという、目眩すら感じる幸福の余韻。 哀しいのは、それを一番与えてほしい人からは与えてもらえないという事実。 一番愛して欲しい人は、私を愛してくれないという、悲しい矛盾。それ故に――……。 「」 突然かかった冷たい声に、躯が強張った。 あれだけ愛しそうに、大切に異母妹を『』と呼んでいた声。 その声が私の名を呼ぶときは、こんなにも冷たい。 底冷えするようなその声が、ただ痛くて……。 「イザーク。食事中だぞ」 「貴様に用はない。引っ込んでろ。俺が用があるのはこの女だ」 「私は、お前に用などない」 震えそうになる声を叱咤して、それでも何とか言葉を紡ぐ。 冷たい、冷たい声。 冷たい人。 そんな目で、私を見ないで欲しい。 そんな軽蔑しきった、まるで汚らわしいものでも見るような目で。 「わざわざ出向いてやったというのに、随分な返事ですね。我が愛しの婚約者殿」 「……ッツ……!」 侮蔑に満ちた、声。言葉。 イザークは、誰かをバカにしたり侮蔑したりするとき、敬語になる。 今も、そうだ。 それだけ……彼が敬語を使うだけ、私は嫌われているということなのだろう。 「いい加減にしろ、イザーク。これ以上を侮辱することは俺が許さない」 「婚約者同士の語らいに割り込む気か、アスラン。無粋の極みだぞ?」 「……アスランに文句を言うのはやめろ。私の気持ちは、この前言った筈だ。私はお前と、用もないのに語らう趣味は持ち合わせていない」 キッパリとそう言いきると、イザークがククッと笑った。 どこまでもバカにしたような、そんな笑い方。 口元は歪んでるのに、目は笑っていない。 いつも、彼は私にはそんな顔をする。 の赤い瞳は「綺麗」で、私の同色の瞳は「気持ちが悪い」そんなことを言う彼のどこから、私への労わりを感じ取れというのだろう。 私への思いやりを見出せというのだろう。 そんな扱いしかしてもらえないのに、どうして私はイザークのことが、嫌いになれないのだろう……。 イザークと同じだけ、イザークを憎めればよかったのに……。 「俺も、貴様などと話をしたいとは思わんが……」 「なら、放っておけばいい」 互いに相手に無関心でいる限り、傷つくことはない。 傷つけられることもない。 「だが……そうはいかない。いかに俺が嫌だといおうが、貴様が俺の婚約者であることに変わりはない」 「なら、断ればよかったんだろう?」 「ジュール家には、家の援助が必要。家は、ジュール家のネームバリューが必要。互いの家の利益が絡んだ問題に、感情だけで否やとは言えんさ」 「それが、どうした?」 家のことなんて、私には関係ない。 あんな父親に、愛情なんて抱けるはずもない。 私を体のいい駒扱いしかしてくれない家を、それでも私は重んじなければならない、と。そういうことか? 「家がどうなろうと、私の知ったことではない」 を殺したのは、父上だ。 父上さえを軍にやると言わなければ、は死なずに済んだ。今も私の側にいてくれた。 あんな父親を、を殺した家を、何故私が愛しまねばならない? あんな家、どうとでもなるがいい。 「貴様を育てた家だというのに……。恩を返すという発想すらも貴様にはないのか?」 「関係ない。あんな家、どうとでもなるがいい」 を殺したのは、家。 そして父様は、母様が亡くなるまで、娘とも遇してくれなかった。母様が亡くならなければ、父親としての責任すらも果たそうとはしなかっただろう、卑怯者。 そんな男に、傾けるべき愛情など私は持ち合わせてはいない。 「用がそれだけなら、私はこれで失礼する。……アスラン、ミゲル先輩。申し訳ありませんでした。食事中に不快な思いをさせてしまって」 「いや、気にしなくてもいいが……」 「、ちょっとやばいよ。イザーク、本気で怒ってるよ」 「怒るなら、どうぞご勝手に。私のいないところで好きなだけどうぞ。私の愛しい婚約者殿?」 言いすぎだ、とアスランは思ったのだろう。 相手は、イザークなのだ。下手に刺激してはいけない。 端麗な、そして冷たい美貌をしているため分かりにくいが、イザークは決して穏やかな人柄ではない。 彼は例えるなら、ぐらぐらと沸騰しきった高熱の熱湯のようなものだ。 少しでもその意に反するようなことがあれば、遠慮会釈なく怒気を発散させるだろう。 「エザリア様の言いつけかどうかは知らないが、私は感情を持たない人形ではない。お前たちの都合に、つき合わされなくてはならない理由など無い。どうしてもそれが気に食わないなら、いくらでも破談にしろ。私はなんとも思わないから。それとも、母上がいなければ何も出来ないのか?ジュール家のご子息殿は」 「何……だと、貴様!」 「!それ以上はよせ!」 アスランの声に、漸く私は、自分が言いすぎたことに気づいた。 アスランの隣では、ミゲル先輩が溜息を吐いている。 これだから、お前の気持ちはイザークに伝わらないんだ、と。 そういわれているような気が、した。 「話がある、来い!」 「話ならここでしろ。お前に従う義理など私にはない」 「可愛げのない……とは大違いだな!」 ……そんなこと、分かってる。 血の匂いのしない、。 父上に命じられるままに前線に出て、血の匂いしかしない私。 比べるほうがおかしい。 辛いことも、苦しいことも経験したことのないと私は、違う。 銃を……ナイフの柄を握る続けた私の手は、今ではもう男のもののようにごつごつしている。 これはとても、女の手なんかじゃない。 そしてそれ以上に、私は、じゃないのだから。 あの子のように、愛されて育った娘とは、違う。 勿論、母様とは私を愛してくれたし、私も二人を愛した。 けれど二人が亡くなって以降、誰が私に愛情を注いでくれた? 父様は、ただ私にの代わりに軍に行けと、それだけだった。 は……あの子は私を一度も姉だなんて認めてはいなかった。 冷たい拒絶の中で暮らしてきた、そんな私の気持ちが、絶望が、イザークに分かる筈がない。 のいいところ、素晴らしいところしか見なかった、あの子に夢だけを見ていたイザークに、分かる筈がないのだ。 夢を抱くのは、勝手だ。 けれどそれに、私を巻き込むな。 私にそんなものを求めても、私は応えられない。 私はあの子とは違う。 私は、私なのだ。私は、『』以外にはなれない。 ――――『一刻も早く、俺はをこの家から解放してあげたい。 そのためには、力が必要だから。そのために、俺は軍に入るんだ』―――― 二人がいなくて、私が幸せになれるはずがない。 。母様。私を愛してくれた唯一の、私の肉親……。 あの頃に、帰りたい。 例えその時の私の身分が、とてもイザークとつりあわなくても。 一生見ているだけの恋だったとしても、私はそれでも幸せだっただろ。 その幸福を抱いて、死んでもいいと思えるほど。 私の幸せなんて、そんなものなのだ。 大それた夢を望みは、しない。 望んだこともなかったはず。ただこの日々が永遠に続けばいいと願い続けた、その幼い夢すら無残に砕け散った。 望んだ永遠も、幼い日に抱いた恋すらも、今の私には残されていない。 自分を憐れもうとは、思わない。 世の中には、私以上に苦しんでいる人もきっとたくさんいる。 この程度のことで自分を憐れむことは、そんな人たちに非常に失礼だ。 少なくとも私は飢えることも、寒さに震えることもない。 前線に出て、闘い続ける。ただそれだけが、他人から見れば私の不幸なのだろう。 私の不幸なんて、その程度なんだ。 誇り高くあれ、と。母様は私たち兄妹に言った。 どんな惨めな生活を送ろうとも、誇りだけは忘れるな、と。気持ちは落ちぶれるな、と。 それは、母様から私たちへの、教訓だったのかもしれない。 母様が亡くなれば、私たちは家に引き取られ。 家に行けば、待ち受けているのは忍耐の日々と。母様はおそらく分かっていたのだろう。 けれどその教訓が、私たちをここまで連れてきてくれた。 誇り高く生きて死んだ、母様。そして。 私と同じ年なのに、私のことだけを考えて、自分の幸せすら棒に振って、前線に出て事故死した、優しい双子の兄。 愛しい人たち。だからこそ私は、二人を殺めた家を許せない。 そしてだからこそ、私は常に私を大切にしたいと思うのだ。 私を愛してくれた優しくも愛しい人たちに、応える術などそれくらいしかないから……。 「さすが、下賤の生まれは違う。人の話すらまともに聞けないのだからな!」 「……何だと?」 「さすが、ルーク=氏を誑かした女の娘と、褒めてやってるんだろうが?」 「貴様……ッッ!!」 母様が、父様を誑かした、だと?違う!父様が勝手に母様に手をつけて、外聞が悪くなって私たちを捨てたんだ! 母様は、そんな女性じゃなかった。 美しく、誇り高い。そんな女性。それを悪くいう人間は、私は絶対に許せない。 「訂正しろ!何も知らないくせに、さっきからべらべらと勝手なことを……!貴様如きに、私たちの何が分かる!!」 「あいにく、下流の人間の考えることなど分からんな」 「あいつらの……父上との肩だけを持つお前に、分かる筈がない。私たちの気持ちなんて……と母様のことなんて……知らないくせに、勝手なことを言うな!!何も……何も知らないくせに……」 私たち兄妹を育てるために、無理をした母様。 私のために軍に入った。 二人を侮辱することは、私には許せない。 私はその暴言を、許容することなんて出来ない。 何故、こんなことを言われなければいけない? 誰よりも愛している人が紡ぐのは、どうして私への嘲りの言葉なのか。 何故……何故『あの日』のように、微笑んでくれない? 何故、彼から愛されるのが私ではないのか。 何故、彼が愛したのは私ではなく、だというのか。私の方が、あの子より先に彼に恋したのに――……!! 胸が、苦しい。 痛くて。彼の言葉は、いつも私には痛くて。 いつも、私を痛めつける言葉しか、彼は紡いでくれない。 少しでいいから。優しい言葉をください。 少しでいいから。それ以上は望まないから。 「貴様のことなど、知りたいとも思わん。俺はただ、ジュール家のために貴様の家の援助が必要だからこそ、貴様との婚約を承諾しただけのことだ。だが……」 「何をする!離せッッ!!」 「いくら『赤』を許されようが、所詮は女だな。俺に力で適う筈がないだろう?」 「イザーク!を離せ!」 突如、強い力で抱きすくめられて、息が止まるかと思った。 彼が愛用しているフレグランスの香りに、頭がボーっとなる。 それくらい、今の私は、彼のすぐ傍にいた――……。 「無粋だぞ、アスラン?婚約者同士の話に、割りこむつもりか?ザラ家の子息ともあろうものが……」 「イザーク、もうよせ。も言いすぎたが、お前も言いすぎだ。ここは退け」 「貴様にどうこう指図されるいわれはない、ミゲル。この女は俺の婚約者だ」 アスランとミゲル先輩が、イザークを止めようと腰を浮かす。 揶揄するように、イザークはそんな二人に笑った。 嫌な、嫌な笑顔。痛い。痛い――……。 肩を抱いたまま、イザークはドアに向かって歩いていく。 心は拒絶しているのに、躯はイザークに従順だった。 促されるままに、ドアに向かって歩く。 つれてこられた先は、私室、だった。 それも、イザークと私の部屋にと宛がわれた――……。 扉が開き、室内に突き飛ばされる。 衝撃はあったが、痛みはなかった。 戦艦の中にあって、不釣合いなダブルベッド。 私が倒れこんだ先は、そこだったから――……。 「はじめに言っておくが、俺は貴様なんぞどうでもいい。強いて言うなら、貴様が死ねばよかったと思っているくらいだ」 「……知っている」 「だが、それでも婚約者は婚約者だからな」 知っている、そんなこと。 彼は私が死ねばよかったと思っている。私が生きているのが不満なのだ。 死んだのが、ではなく私であったらと。そう思っていることくらい、私だって知っている!分かっている……。 「私の本意じゃ、ない」 「本意であろうがなかろうが、そんなことはどうでもいい」 「何を……!?」 イザークがのしかかってきて、その手で私の手首を戒める。 咄嗟のことに身動きすら出来ずに、ただその力の強さに身を捩った。 イザークは、ただうっすらと微笑んで。 更なる絶望へ、私を叩き落した。 「婚約者としての責任、果たしてもらうぞ?。その躯でな」 「嫌だ……やめろ……ッッ!!」 怖くて。捩じ伏せられる恐怖に、ただ恐れだけが私の中にあって。 歪む私の顔を、満足そうに見下ろしたイザークが、ふっと優しげな笑みを口元に刷いて。 睦言を囁くかのように甘く、私を奈落に突き落とした――……。 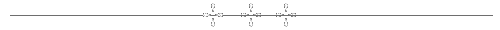 だから、こういう話なんです。 あまり切ない話ではないと思うのですが……。むしろ、えげつない? はは。否定できませんねぇ。 て言うか、イザークいい加減酷すぎるな、この性格。 このあとは、裏に続きます。 裏が読めなくてもお話は通じるように書きますので、ご安心くださいね。 こんな話(本当にな)をここまで読んでくださり、本当に有難うございました。 |