|
そして同時に認識する、避けがたい現実。 死ぬのか……そう、思った。 それが、現実だった。 真っ白い光が、ただただリアルで。 そんな中。 死ぬのか、と。 ただ、それだけを考えた――……。  番外編2 最期の、夢 =という少年は、綺麗な少年だった。 いわゆる、美少年てやつかな。 艶々した漆黒の髪だとか、大きな紅玉の瞳だとか。 あぁ、コイツ軍人に向いてないわ。そう思った。 勿論、それは彼が綺麗だったから、というのが理由ではなく。 彼の瞳は、脆そうだった。 生きる欲求が希薄というのか。 彼からは、生への執着を殆ど感じなかった。 戦場での働きには、目覚しいものがあった。 己の身を省みず、敵に向かって突撃する。 そんな戦い方は、なかなか出来るものではない。 軍人を選んだ理由は、人それぞれだ。 けれどその殆どに共通するのは、『大切な人を守りたい』それだと思う。 そしてそう思う人間は、同時にこうも思うんだ。 『大切な人を、守りたい。その人が、自分の隣で笑ってくれたら……』 って。 死ぬなって感じたときなら、自分の命と引き換えに、彼の人をお守りください、と願う。 けれどそうでないときは、違うんだ。 幸せなあの人の隣で、自分も笑っていられたら、と。そんな幸福を、夢見るんだ。 だから、なかなかそんな戦い方は出来ない。 死ねば、哀しむことが分かっているから。 死ねば、泣くことが分かっているから。 愛するその人が、何者にも変えがたい大切な人が、幸せであるように、と。それを願うのであれば、生きたいと思う。それは当然の、感情の帰結だと思う。 でも、あいつは違った。 綺麗な瞳を、していた。 傷ついてきた人間の瞳だ、と思った。 脆い脆い、瞳。 内包する魂もきっと、脆いのだろう、と。戦場で生きるにはそぐわない、と。直感的に思った。 初対面で口にするには、かなりの言葉を、口にした。 「お前、軍人に向いてないんじゃない?」 「……そう、ですね。俺も、そう思います」 無理矢理、『俺』の一人称を使っている感じだった。 少し、一人称がぎこちないな、と思った。 本当にさ、なんで軍人なんかやるわけ?って思ったよ。 別に軍人なんて、やらなくてもいいじゃないか。 「俺の父は、ルーク=です。父が主戦を主張するのに、その息子がプラントで安穏と暮らすわけには、いきません」 「……そんなもん?まじめだねぇ」 家。名前は、聞いたことある。 俺の家は、ごくごく普通の一般家庭で、家自体とは縁がないけれど、テレビなんかではよく騒がれている。 最近力をつけてきた、成り上がりの家。 当主のルーク=は、かなりのやり手と評判だったっけ……。 「それに……」 「それに?」 「あ……なんでもありません。すみません、変なことを言って」 今なら、『それに……』に続く言葉も分かるけれど。 その時の俺は、分からなかったんだ。 『それに……私は家には不要な娘なので、死んだとして生きるしかない』 そう、続いたのだろう、と。 今では簡単に、予想がつく。 彼の生への執着の希薄さ、その時感じたものを、俺は誰にも言わなかった。 弟ができた気持ち、だった。 もう一人、弟が出来た気持ち。 繊細な瞳をした、壊れそうに脆そうな心を抱えた少年を、守らねばと。 兄の気持ちで思った。 俺が、守るのだ。 俺が、支えてやるのだ、と。 そうでなければこの少年は、あっという間にこの世からその存在を消してしまうだろう、と。 ただ漠然と感じていた。 この少年をこの世に留める細い細いしらがみの一つにでもなれたら、と。そう願った。 だってあまりにも、哀しすぎる。 生きること、その全てが幸福なんて、俺は言わないし思わない。 でも、何の喜びもなくただ薄いガラスを隔てたようにしかこの世と接触できない少年が、哀れだった。 言ってやりたかったんだ、おそらく。 『お前は、必要だ』 と。その一言だけでも、少年をこの世に繋ぎとめられると、ただ感じていたんだ。 兄の気持ち、だった。 もう一人、弟が出来た気持ち。 それだけだった。 「=、入ります」 ウェーブがかった黒髪を下ろして、女性用軍服を纏ったに出逢うまで、俺はが女で、という名の少女であることに、気づきもしなかった。 そりゃあさ、男にしては線が細すぎる、とか。 こんな綺麗な男、いるわけないとは思っていたけど。 あの潔さは、女ではないような気も、どこかでしていた。 他のどの女よりも潔く、哀しい少女。 それが、――――だった。 初めて見た、女性としての彼女。 それでも他の女とは全然違った、彼女。 そんな彼女に、痛いほどの恋情を自覚しなければ、俺は一生、恋とは無縁の人生を送っていたのかもしれない。 愛しい、と思った。 始めは勿論、妹みたいだと思ったけれど。 そうじゃ、なかったんだ。 俺は彼女を、いつの間にか愛するようになっていた。 兄の妹に対するような、穏やかな凪のような感情ではなく。 俺は彼女に、『女』を見るようになっていた――……。 分かっていたんだ。 決して叶わぬ恋であることくらい、分かっていた。 俺が愛するのは、=。 けれど彼女が愛するのは、イザーク=ジュール。 分かりきっていたこと、だった。 彼女の瞳はいつも、イザークだけを見ていた。 脆い脆いガラスみたいな、現実から剥離したような瞳は、イザークを見るときだけ熱を帯びる。 分かって、いた。 でもそんなこと、どうでもよかった。 愛しい、と想った。 傍にいて欲しいと願い、彼女のためなら、と想った。 のためならば、と。 彼女が誰を愛しているとか、彼女が俺を『兄』以上に見ることはない、とか。 そんなことはどうでもよかった。 傍にいて、笑ってくれたら、それでいい。 それ以上を望まない。 俺は、『兄』でいい。 が幸せなら、それでいいと。そう思い込むほどの激しい情熱。 今まで持ったこともないそれは、ただ一人の少女を対象に動き始めていた。 =。 漆黒の髪に、紅玉の瞳。 脆い……でも毅い少女。 愛しい、と想った。 そう想うことすら彼女を穢しているみたいで、そんな自身の感情に、悶えんばかりの焦燥を味わった。 それでも、その存在は絶対。 それでも、少女は至上の人。 愛してる。でも、無理強いはしない。 それは、俺が物分かりがいいとかそんなことではなくて。 ただ彼女が、それほどに価値ある存在だったから。 無理に思いを告げることも、刹那的欲求の甘さに浸ることも許せないほどに、彼女に焦がれたから。 ただ、それだけ。 だから、お前が気に病む必要はないんだよ、。 それが、真実。それだけが、真実。 傍に、いて欲しかった。 笑っていて欲しかった。 幸せになって欲しかった。 脆い脆い瞳をしていた少女。 幸せを夢見ることすら放棄したような少女。 傷つきすぎるほどに傷ついてきた少女。 彼女に、幸せになって欲しかった。 自分がその害になるならば、いくらでも己のこめかみに拳銃を突きつけてやれるほど。 何の躊躇いもなく引き金を引いてしまえるほど、焦がれたから。 だから思い告げた今、望むのはただ一つだけ。 が幸せであること。 そして……欲を言うなら、もう一つ。 恋人になれなくてもいいから、己が彼女の中で絶対の位置を占めることが出来ること。 それだけ。 『兄』でいい。必要なとき、彼女が真っ先に頼れる存在であるならば。 それで、いい。 それ以上は、望まない。 真っ白な、光。 目を灼ききるほどの、強烈な閃光。 その先に、あるものは、明確な死だと言うこと。 それが己の現実であることを、認識して。 嫌だ、と叫び声を上げる。 彼女を、守れなくなる。 自分を否定し続けた少女を。その身を戒めるしがらみの一つにでもなりたいと願った存在を。 俺の死は、一つのしがらみの消滅。 彼女を現実に繋ぐ不可視のしがらみとしての生は、その死を持って終わる。 そんなことには、耐えられない。 守って、やりたかった。 傍に、いてやりたかった。 傍にいて、いってやりたかったんだ。 お前は必要だ、と。俺は必要としている、と。 ただ、それだけだった……。 「今度泣かしてみろ、イザーク。許さねぇからな」 自嘲交じりに、呟く。 分かって、いた。 生きては還れない。分かりきって、いた。 戦場に在ったその勘が、告げていた。 ――『お前は、生きては戻れない』―― と……。 泣きたくなるほど、情けない。 けれど同時に、安堵する自分もいた。 これで、とイザークと。二人の出す明確な結論に関わらずにすむ。 愛したから、耐えられない。 他の男の腕に抱かれて微笑む、少女。 だからこれで、よかったのかもしれない。 不可避の現実として死が迫って漸く、そう思えた。 これはある種、幸せなことと。 ただ願うなら、もう一度。 もう一度だけ、少女の笑顔が見たかった。 愛した少女の、笑顔。 愛した、温もり。 それがもう、描けない。 「やっぱ俺……お前が好きだわ、……」 そっと、囁く。 愛しさを、万感のいとおしさを乗せて、唇が紡ぐ、その名を。 囁いて。 大きく腕を広げて迫りくる『死』の背後に、愛した少女の笑顔を認めた気がして。 少しだけ、笑いたい気持ちになった。 「愛してる、……」 だから、お前はまだ、こっちにはくんなよ? 続く光の奔流に、囁きは、そして彼の意識すらもかき消され、飲み込まれる。 呟くその名も、愛した面影も一緒に飲み込んで、彼と言う存在を消し去る、白い光。 それでも、彼はうっすらと笑った。 その光の先に、愛した少女の面影を、確かに見た、と。 彼は笑って――……。 最期に見た夢は、ただ眩しく。 抱いた灼熱の炎は、優しかった――……。 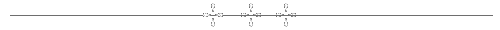 『恋哀歌』としてのミゲルの死に、自分で一応のけりをつけてしまいたかったのです。 ヴァルキュリアと違い、ヒロインに明確な恋愛感情を抱いていたミゲルだからこその、結末を。 愛しているが故の、その想いの美しさ。愛しているが故の、自己満足的な願望。 そう言ったものを一度、自分で消化してしまおう。 そう思って書きました。 表現できているかは非常に謎ですけど、書けて満足です。 一応、ヴァルキュリアとは少し、ミゲルの気持ちに温度差を出したつもりですけど……どうでしょうか。 それでは、ここまで読んでいただき、有難うございました。 |