|
無理して笑わなくてもいいよ 好き。 兄さんが、好き。 誰よりも、貴方が好き。 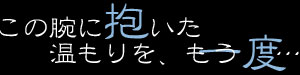 最近出来たばかりのその喫茶店の名物は、ガトーショコラ。 ほろ苦いケーキ生地にミントを添えたホイップクリーム。 ケーキの上には、粉砂糖が飾られている。 「美味しそう」 「ガトーショコラだけでいいのか?お前、そっちのイチゴのショートケーキのほうが好きだろ?」 「でも、名物はこれだって言うもん」 「どうせお前、ケーキの二個ぐらい楽に食えるんだから、二つにすればいい。飲み物は?」 「お二人さん、イチャイチャしすぎ」 後から呆れたようにかかる声に、アスランとイザークは慌てて離れた。 金糸の髪をガシガシとかき上げたミゲルが、悪戯っぽくニカリと笑った。 ガラスウィンドウの前に張り付いたアスランは、慌ててミゲルも前に来るよう言った。 ウィンドウの前でメニューをちらりと見ると、ウェイトレスにミゲルが注文を始める。 「俺はビスコッテとエスプレッソ。イザーク、お前は?」 「……俺も食うのか、やっぱり」 「そりゃそうでしょ?お前は?」 「……ブレンドとスコーン」 「アスランちゃんは?」 「ガトーショコラ」 小さく答える。 兄とアスランの顔は決して似ていると言いがたいから、人前で一緒にいても恥ずかしいことはない。 けれど恥ずかしいと思ってしまうのは、アスランが兄に恋心を抱いているからだった。 「それとイチゴのショートケーキ。あとカラメルマキアート」 「兄さん?」 「支払いは……」 「イザーク。支払いは俺がするよ。まさか後輩とその妹ちゃんに奢らせるわけにはいかないからさ」 バイトしてるし、先輩に任せなさい、なんて。 おちゃらけて言う兄の先輩に、アスランは小さな声で、けれどはっきりと礼を言う。 有難う、とごめんなさいはしっかり言うように。兄は昔から、口をすっぱくしてアスランに言うのだ。 面白いのは、そう言う本人はちっとも素直にそう言えない所だろうか。 注文をして支払いを済ませると、小さなカウンターの方に行くように言われる。 この店は、基本的にセルフサービスのようだ。 カウンターの方に行き、レシートを示すと、注文したとおりのコーヒーを目の前で淹れ、ケーキが出される。 結構な量だから、ミゲルとイザーク、二人で席までそれを運んだ。 先に席に着いたアスランは、笑顔で二人を手招きする。 「ほら、アスラン」 「有難う。先輩も、どうも有り難うございます」 「いいって、いいって」 苦笑しながら手を振るミゲルに、アスランは小さく笑った。 それに、イザークが一瞬怖い顔をしたのを、アスランは知らない。 「モカのほうがよかったか?アスラン」 「ううん。これも好き」 アスランの隣に腰掛けながら、イザークが言う。 それに、アスランは僅かに頸を振った。 確かに、甘いものが好きなアスランとしては、モカのほうがよかったかもしれないが、アスラン自身カラメルマキアートは決して嫌いじゃない。 それに、何と言っても大好きな兄が選んでくれたものなのだ。 不満なんて、ある筈がない。 「仲いいねぇ、お前ら」 「うち、両親が不在がちなんです。だから、兄さんとは仲いいですよ?昔から、お兄ちゃん子って言われてたんです、僕」 「へぇ。そうなんだ?」 ミゲルの言葉に、アスランは嬉しそうに頷く。 ずっとずっと、イザークが傍にいた。 寂しい時も、辛い時も。いつも傍にいてくれて、時には慰めてくれた。 そんな兄を、アスランは知らず知らずの内に、愛するようになっていたのだ。 「美味いか、アスラン」 「うん。美味しいよ。あまり甘くないから、兄さんも食べれるかも……。ねぇ、兄さんも一口、食べる?」 「そうか?じゃあ、一口だけな。……クリームはつけるなよ?」 「分かってるよ。……ハイ、あ〜ん」 フォークでケーキを掬って、兄の口元までもって行く。 薄い唇を微かに開けて、アスランの差し出したフォークに食いついてケーキを租借する。 そして微かに、顔を顰めた。 「嘘吐きアスラン。十分甘いぞ、これ」 「えぇ。甘くないよ」 「いや、甘い。……ほら、やっぱりお前は、ガトーショコラよりイチゴのショートケーキだ」 してやったりといった風情で笑う兄に、アスランは微かに頬を膨らませる。 何でも見透かされていたような気がして、少し決まりが悪い。 そんな二人に、ミゲルが笑った。 「いや、大学にいるときのイザークとは大違いだ」 「バカ、ミゲル!」 ミゲルの言葉にバツが悪くなったイザークが、その口を塞ごうと手を伸ばす。 しかしサラリとそれをかわすと、ミゲルは楽しそうに告げた。 「大学での兄さん?」 「そ。酷いヤツだぞ?女にもてるけど、長続きはしないわ付き合っても冷淡だわ」 「それって……兄さん、彼女、いるんですか?」 「オイ、やめろミゲル!」 「いるって言うか、いた?この前別れたばっかりだろ、イザーク」 「ミゲル!」 ミゲルの言葉に、アスランは凍りつく。 確かに、妹の欲目を差し引いても、イザークはかっこいい。 その辺の女なんか、束になっても敵わないと思うほど、綺麗だ。 けれどそんな兄に彼女がいたなんて、アスランは知らなかった。思いもよらなかった。 けれど、そうだ。イザークに、今まで彼女がいなかったと考えることのほうが、おかしい。 これほどの魅力に溢れた青年なのだ、イザークは。 「アスラン、ほら、ケーキを食え。ミゲルも、つまらんことをコイツに吹き込むな」 「へぇ。ひょっとして、妹ちゃんには教えていなかったわけ?イザーク。……教えたら、都合が悪かった?」 悪戯っぽく輝く琥珀の瞳が、それでも挑むようにイザークを見やる。 それに、真っ向からイザークは鋭い視線を叩き込んだ。 「そっか、いたんだ、兄さん……僕、全然知らなかった……」 「いや、それは……」 「どうして、教えてくれなかったの?言ってくれたら、我侭何ていわなかった。休みの日に一緒に水族館に行こう、とか。遊園地に行きたい、とか。見たい映画がある、とか。そんなこと僕、言わなかったよ……?」 「違う、アスラン」 「どこが違うの?兄さん、彼女よりも僕を優先して、そのせいで彼女と別れちゃったんでしょう?」 兄がもてることなんて、知ってた。 それなのに、特定の誰かが既に存在していたなんて、思いもよらなかった。 そこに思い至らなかった自分が、いっそ滑稽に思えてくる。 「アスラン、話を聞け」 「僕に言い訳をする理由がどこにあるって言うの?僕は所詮、ただの妹だよ。そんなの、彼女にしなきゃ」 『ただの妹』 自分で紡いだ言葉だというのに、傷つく自分が少し滑稽だった。 自虐的に笑いながら、わざとらしい仕草でカップの中のカラメルマキアートをすする。 甘いはずのそれが、ほんの少し苦く感じられて、泣きそうになる。 「美味しいです、先輩。本当に、奢っていただいて、有難うございます」 「いいよ、これぐらい。おれも、いい店教えてもらったしね」 「先輩、甘いものお好きなんですか?」 「いや、俺じゃなくて俺の彼女がね。いい店教えてくれて、ホントにサンキュ。今度アイツ連れてくることにするわ。すっげ喜びそう」 「そうですか、それは良かったです」 にっこりと、アスランは笑う。 まだ何かいい足りないらしい兄が、怖い顔でアスランを見ているが、その視線に、アスランも答えるような真似はしない。 口を開けば、何を言ってしまうか分からない。 彼女でもないのに、兄妹なのに、未練たらしく縋りついてしまいそうで、嫌だ。 兄妹なのに、見苦しく理由を問い詰めてしまいそうで、嫌だ。 そんな自分も嫌だし、そんな兄を見るのも嫌だ。 自分と一緒にいるのに、他の事を考える兄なんて、想像するだけでも嫌だ。 結局、その店にいる間中、アスランはイザークを無視し続けたのだった――……。 「アスラン、いい加減にしろ」 帰る道すがら、ずっとシカトし続けるアスランに、遂にイザークが感情を露わにした。 もともと、あまり気の長い性質(タチ)ではないのだ、イザークは。 「何が?」 「そうあからさまに俺をシカトしようとするところだ。いい加減にしろ」 「別にしてないし。兄さんの考えすぎじゃないの?」 イザークの前を歩いていたアスランが、後方の兄を振り返る。 家々の間から微かに覗く月を背にして、微笑(ワラ)った。 イザークは、気づいているだろうか。 その笑顔が強張っていることに。 指先が震えていることに。 平気な顔をして笑顔を作るはずだったのに、どうもアスラン自身、自分の笑顔が強張っている気がして仕方がなかった。 笑わなければ、いけないのに。 自分と彼は、『兄妹』なのだ。それ以外の何者でもない。 それ以上の感情で、触れてはいけない。 「お前、今日は何か変だぞ、アスラン」 「そんなことないよ」 「誰かに、何か言われたのか?いつも、何か言われているだろう、お前。俺のところに来る度に」 「あぁ……」 アスランは、気のなさそうな顔でそう呟く。 別に、誰かに何かを言われたわけじゃない。 ただ、現実を思い知らされているだけだ。 自分と彼は『兄妹』だという、避けようのない現実を。 「別に何もないよ」 「嘘をつけ。だったらどうして、そんな笑い方をするんだ、アスラン」 「ぇ?」 「無理をして笑うな、アスラン」 イザークのてが、アスランに向かって伸ばされる。 その華奢な痩身を、そっと抱きしめて。 耳元で聞こえる、ハイヴァリトンの声。 イザークの、声だ……。 「辛いことがあったのなら、俺に言え。そんな顔をして、笑うな。お前の笑顔は、時々痛いんだ、アスラン」 「兄さん……」 「無理して笑わなくてもいいんだ、アスラン」 「兄さん……」 そっとアスランは、イザークのその広い背に腕を回した。 間近で感じる温もりが、ただ心地よい。 けれど同時に思い知るのだ。 所詮自分たちは、『兄妹』なのだ、と。 零れそうになる涙を、アスランはぐっと堪えた。 そのまま、その耳元に囁くように声を落とす。 「大丈夫……大丈夫だよ、兄さん。大丈夫だから、そんなに心配しないで」 笑顔も嫉妬も。 いつも、貴方という存在にある。 貴方だけが僕を、笑顔にもそれ以外にもすることが出来るんだ――……。  お久しぶりの更新です。 すっかり兄がヘタレてしまいました。 が。このお話も頑張っていきたいです。 いづれかっこいい兄も書けるようになったらいいな、と思います。 それでは、ここまでお読み戴き、有難うございました。 |