|
君がいたから
『だって、僕には兄さんがいるでしょう』 そう言って屈託なく微笑む君に。 みせてやろうか。 際限なく膨らんだ狂気を。 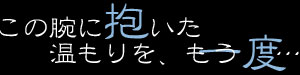 「兄さん、ねぇ、兄さんってば。起きてよ」 ゆさゆさと揺すぶられて、彼は漸く覚醒した。 といってもまだ、寝惚け眼ではあるのだが。 「兄さん、朝だよ。遅刻する」 制服の上からエプロンをつけたアスランの姿が、あった。 食事は大体、アスランが作るのが日課になっている。 彼だって料理は得意なのだが、それだけは昔から、アスランがやりたがっていたのだ。 一応メイドもいるが、アスランの好きなようにさせている。 怪我をすればことだが、今のところ大過はない。 「兄さん、朝ご飯冷めちゃうよ」 「……今日は二限から」 枕に顔を埋めたまま、イザークは答えた。 くぐもった声に、アスランが一瞬赤面するが、イザークにはそれが何のことやら分からない。 制服の上からつけたエプロンは、アスランの好きなオリーブグリーンのものだ。 機能的なそれは、イザークがアスランに買ってやった。 アスランは見てくれからは想像も付かないが、粗忽者の一面があったからだ。 イザークが買ってやると、アスランはイザークが大好きな笑顔を浮かべて有難う、と言った。 それ以来いつも、アスランは料理をする際はそのエプロンを使っている。 今も、そうだ。 「もう少し寝かせてくれ、アスラン。昨日遅かったんだ。今日は二限からだし……」 「朝ご飯、冷めちゃうよ」 「後で温め直して食べるから」 「一人でご飯食べても、美味しくないよ……」 彼の言葉に、妹はシュンとした様子で答える。 罪悪感を覚えてしまうほど、その様は頼りない。 「……分かった。起きる。今日の朝は、何だ?」 「フレンチトーストとスープ、それにサラダ。そしてカフェ・オ・レだよ」 「カフェ・オ・レはブラックコーヒーに代えてくれ、アスラン」 「一緒にご飯食べてくれるなら、代えてもいいよ」 ニコニコと、邪気のない様子でベッドに横たわる彼を少女は見下ろす。 彼のベッドの傍に跪き、肘をついて掌で頬を支えるその格好で。 一瞬、朝からこれは何の拷問だ、と彼は思った。 朝から理性を試されている気がするのは、気のせいだろうか。 これ以上はさすがに目に毒な光景から目を逸らすべく、彼は起き上がった。 均整の取れた躯を起こし、足を地に付けた。 それから、着替えをするべくクローゼットを開ける。 「着替えるから、さっさと部屋から出ろ、アスラン」 「何で?」 「何で?じゃないだろ。さっさと出て行け」 きょとんとした顔で尋ねる妹に、彼は溜息を吐いた。 一体どれだけ自分が耐えているのか、この妹は理解しているのだろうか。 あぁいっそ、もういっそ。 いっそこの均衡を、突き崩してしまえ、と。 身の内に潜む狂気が囁く。 いっそ、いっそのこと。 この妹を、自分のものにしてしまいたい。 自分だけを見るように、自分だけを想うように。 突き動かされる渇望に、彼の手がその妹に向かって動いた。 「兄さん?」 あどけない声で、顔で、妹が彼を見上げる。 それに、彼ははたと手を止めた。 朝から、何を考えているのだろう。 ばかばかしい。疲れているんだ、きっと。 この恋は、叶ってはならないものだから。 どれだけ手を伸ばそうと、どれだけ渇望しようと。手に入らないものだから。 そんな感情にきっと、倦《う》んでいるのだろう。 「いいから、出ろ。着替えるといっているだろう」 「別に、僕の目の前で着替えてもいいじゃない」 「アホか、お前は」 いって、彼はベッドのところに陣取る妹を、部屋の外へと押し出した。 まったく、冗談じゃない。 無防備な妹の前で、肌を晒して。 そんなこと、出来るわけがない。 そんなことになったとき、その後の自分の行動こそが、恐ろしい。 無防備な妹に。おそらく自分を兄以上の目では見ていないだろう妹に。 何をしてしまうか。 それこそが、彼は恐ろしかったのだ。 堪えがきかなくなる、そんな渇望。 欲しいものは、目の前に在って。 目の前で無防備に屈託なく、彼に微笑んで。 それなのにその存在を、手にすることは叶わない。 それは、どれほどの責め苦だろう。 本当に欲しいものは、目の前に在るのに。 目の前に在って、微笑んで。 それなのにそれを手にすることは、叶わぬのだ。 彼らを取り囲む世界が、それを決して赦しはしない。そんなことは、分かっている。 それなのに。 あぁ、それなのに。 欲しくて、欲しくて堪らない。 今すぐにでも、自分の物にしてしまいたいのに。 あの無防備な瞳を。屈託なく見つめてくる瞳を。 白い肢体もその髪の一筋まで、自分だけのものにしたくて堪らない。 「兄さん、まだ〜?僕、学校に遅れちゃうよ」 「すぐ行く!」 「もぅ。遅れそうになったら、兄さんに責任を取ってバイクで送ってもらうからね!」 「はぁ!?」 妹の言葉に、彼は素っ頓狂な声を出した。 今、何と言った。 この妹は、一体何を。 「当たり前でしょ。ちゃんとメットも持ってるから、安心していいよ」 安心できるか! 思わず彼は、天を仰ぐ。 それは一体どんな拷問だ。 慌てて彼は時計を見た。 時刻はまだ7時を回ったばかり。 まだ、大丈夫だ。 シャツを引っ掛け、ブラックジーンズに足を通す。 手早く髪を手櫛で梳くと、リビングに向かった。 「おはよう、兄さん」 「あ……あぁ、おはよう」 「ほら、早くご飯にしようよ」 「あぁ……」 頷いて、席に着く。 ニコニコと微笑みながら、妹が料理を並べていく。 熱々のフレンチトーストからは、ミルクの甘い香りがした。 エプロンを外して、アスランも彼の目の前に座った。 ブレザーの上着は着ずに、シャツの上にベストだけだ。 黒のプリーツスカートから覗く足が、眩しくて。思わず視線を逸らす。 そんなところに目の行く自分が、そんな目で妹を見ている自分が、妹を見るだけで視線で妹を汚しているような、そんな錯覚に陥った。 「はい、兄さん。コーヒー」 「有難う」 「父さんたち、今日も遅いのかな」 彼らの両親は、そろって忙しい人だった。 家に帰ってくることも、滅多にない。 それでも愛情だけはふんだんに与えてくれていると、思っているから。それだけは、彼も妹も、理解していた。 「多分、遅いんだろうな」 「そっか……」 「あぁ、アスラン、俺も今日は遅くなる」 「え?」 彼の言葉に、アスランは不安そうにその翡翠の瞳を歪めた。 それに罪悪感を覚えるが、彼にも事情と言うものが存在するのだ。 おいそれと、妹の傍になど、いられない。 弾みで一体、何をしてしまうか、分からないのだから。 だから、傍になど、いられない。 「どうしたの?何か用事?」 「ゼミのコンパ」 「……へぇ」 彼の言葉に、妹は冷たい調子で相槌を打つ。 普段の彼ならば欠席するだろうものだが、今となってはその存在が有難い。 時間つぶしに悩むでもなく、少しでも家にいなくてすむのだから。 「いいご身分だね、大学生は」 「……すまん」 心にもない謝罪の言葉を口にしながら、朝食に手を伸ばす。 傍になど、いられる筈がない。 その存在が、確かに喜びであると言うのに。 歓喜も絶望も、全ては彼女の上にこそあるというのに。 イザークの感情の全ては今、彼女の上にこそあるのに。 けれど、その存在が彼をまた苦しめる。 紛れもなく血が繋がっていると言う、それだけの理由が。 彼を苦しめ、戒める。 彼女がいるからこそ、苦しくて堪らない。 「別にいいけど。あ、食器は適当に直しといて。僕、学校に行って来る」 「アスラン?食事は……」 「食欲がなくなったから、いい。学校に行く。……それじゃ、兄さん。行って来ます」 さっさと席を立つと、ブレザーの上着を引っ掛ける。 無言で玄関に行くと、黒のローファーに足を通した。 その姿を、彼もまた玄関まで見送る。 「早めに帰ってくる」 「いいよ、別に。ごゆっくり」 ばたん、と扉が閉まった。 不機嫌な様子で、出かけていった妹。 おそらく、寂しいのだ。 一人きりで広い部屋で過ごすことを余儀なくされるから、寂しいのだろう。それだけだ。期待してはいけない。 「くそっ……!」 がん、と壁を殴る。 君がいたから。 君がいたから、幸せで。 君がいるから、苦しくて堪らない。 見せてあげようか、その綺麗な瞳に。 見せてあげようか、穢れなど何も知らぬげな、無垢な君に。 見せてあげようか。 身の内に詰まったどす黒い狂気を。 君がいたから、幸せなのに。 君がいるから、苦しくて。 だから、見せてやろうか。 この心が抱えた狂気を。 愛しい愛しい、妹。 君がいたから、幸せなのに。 君なしの生など、考えられぬほどなのに。 それなのに君と言う存在が同時に、俺を脅かす。 突き動かされる、本能に。 見せてあげようか。 君がいたからこそ導き出された魂の軌跡。 見せてあげようか。 君という存在が、俺を君から離れられなくした。 君が、いたから……。  やっぱり、兄がヘタレます。 妹のほうが強いんじゃなかろうか。 余談ですが、実は兄妹じゃなかった、なんてそんなオチはありません。 似てはいませんが、この二人はちゃんと血が繋がってます。 れっきとした兄妹です。 そういう展開にはしませんので、ご安心(?)を。 ここまでお読みいただき、有難うございました。 |