|
こいのうた
ずっとずっと、僕だけを見ていて。 お願いだから、女として僕を見て。 僕を愛してよ。 そう願ってしまうのは、僕の我侭ですか――……? 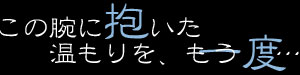 「違う。朝食」 教室でもぐもぐとパンとカフェ・オ・レを食するアスランに、キラが声をかける。 キラ=ヤマトは、アスランの親友だ。 そして、幼馴染でもある。 幼いころは何をするにも一緒だったが、さすがにこの年にもなればいい加減お互いを異性とも認識して、以前ほどの交流はなくなった。 更に言うなら、キラは家庭の事情でアスランの隣家から引っ越していた。 もっともそれでも、今も変わらずにお互いを親友として認識しているわけだが……。 「何だって今日はご飯食べてこなかったのさ?いつも、イザーク兄さんと一緒に食べてるじゃない」 「……その名前を言うな」 「……何かあったわけ?」 アスランの言葉に、キラが尋ねる。 もぐもぐとパンを食べるアスランは、不機嫌そうにむっつりと黙ったままだ。 アスランにとってキラが幼馴染であるならば当然、イザークにとってもキラは幼馴染となる。 1つ年上の頼れるお隣のお兄さんを、キラは昔から『イザーク兄さん』と呼んでいた。 「あんな馬鹿兄のことなんて、知らない」 「馬鹿兄って。 ……イザーク兄さんに向かってそんなこと言えるのは、アスランだけだよ、きっと」 はぁ、とキラは溜め息を吐いた。 苛々としながら、アスランはそんなキラを見つめている。 それでも食事の手を休めないあたり、さすがというところだろうか。 ぐっと、紙パックのカフェ・オ・レを呷る。 まさにその、瞬間。 「アッスラ〜ン!おはよう〜」 椅子に座ってもぐもぐと食事をするアスランの後ろから、タックルをかまされる。 一瞬喉を詰まらせたアスランだったが、根性で口の中の物を飲み込んだ。 ゲホゲホと咳き込むと、邪気のない笑顔で少女が笑っている。 アスランの友人、ミーアだ。 「や……やぁ、おはよう、ミーア。一瞬危うく三途の川が見えたよ」 「やだ、アスランったら。朝から面白い冗談ね」 「……冗談じゃないから」 「ふふ、相変わらずだね、ミーア。おはよう」 「……おはよう、キラ」 アスランとミーアの会話に、堪えきれないといった調子でキラが笑う。 笑顔のキラに、ミーアは明らかにテンションダウンした調子で挨拶を返した。 その理由を知っているからこそ、アスランはミーアのそんな笑顔が痛い。 「そういえば、オリコン一位おめでとう、ミーア」 「チェックしてくれたの?アスラン」 「勿論だよ、ミーア。良かったな」 「ええ」 アスランの言葉に、ミーアは嬉しそうにふふふ、と笑った。 「きっとラクスも喜んでいるよ、ミーア」 「そう……かしら」 「そうだよ。だから、何時までも負い目に考えちゃ駄目だ。ねぇ、キラ?」 「そうだよ、ミーア」 アスランの言葉に、キラも力強く頷く。 ミーアのフルネームは、ミーア=クラインと言う。 事故死した歌姫、ラクス=クラインの、彼女は双子の姉妹だった。 そしてキラは、ラクスの恋人だったのだ。 双子の姉であるラクスに常に劣等感を感じていたミーアはだからこそ、キラの前だと萎縮してしまう。 そこに見える姉の影に、怯えるのだ。 アスランもキラも、そんなミーアにかけるべき言葉は、見つからない。 それは、ミーアが自分の力で乗り越えねばならない壁であるからだ。 けれどそれでも、何かあれば何時だって力を貸す気でいる。 彼らは、そんな関係だった。 「それにしても、どうしたの?アスラン。こんな時間から、早弁?」 「ホームルーム前に早弁はしないよ、ミーア。これは朝食」 「いつも朝食はジュール先輩とじゃなかった?態々《わざわざ》朝っぱらから叩き起こしてでも一緒に食べるんでしょ?」 「ミーアまで……あの馬鹿兄の話はやめてくれ」 『馬鹿兄』の一言で、ばっさりと実の兄をこき下ろすアスラン=ジュール。 余談だが、アスランの兄は昨年の生徒会長でもあった。 「『馬鹿兄』って……何かあったの?アスラン」 「……最近、帰ってくるのが遅いんだ」 ミーアの問いにたっぷり数十秒ほど時間をかけて、アスランが答える。 瞬間、二人揃って『何言ってるんだ』とでも言いたげな顔をするが、アスランにしてみれば死活問題なのだ。 以前ならば、一緒にテレビを見たり、映画を見たりして過ごしていた。 休みの日は一緒に出かけたし、学校帰りにお茶したり。 それなのに、そんな兄は最近帰りが遅い。 急にバイトを始めてしまったり、やれ教授に呼び出されているのと、家を空けてばかりだ。 避けられているの、だろうか。 ふと、アスランは考えた。 ひょっとしたら自分の気持ちが、兄に知られてしまったのだろうか。 麗しく潔癖な兄はアスランの邪念に気づいて、それで……疎ましく思っている? 「それで?」 「それで……うん。それで、今日はゼミのコンパで遅くなるって」 「あら、ゼミのコンパなら仕方がないじゃない」 「僕は家で一人なのに?自分は外で女引っ掛けて遊ぶって言うんだよ、あの馬鹿兄は!」 憤懣《ふんまん》やる形《かた》無しといった風情のアスランだが、他の二人の同意は得られない。 アスランだって、本当は分かっている。 これは、自分の我侭だ。 駄々をこねて、自分の思い通りにならない兄に焦れているだけ。 自分だけを見て、自分だけの傍にいて、と。子供のように繰り返しているだけなのだ。 「じゃあ、アスランもコンパ、行ってみる?」 「ミーア!」 ミーアの提案を、キラが諌める。 が、アスランはその提案に飛びついていた。 「何?何?」 「合同コンパ。クラスの子でも他の学校でもいいから男の子も誘って、セッティングしてあげるわよ。アスランが希望するなら」 「アスランに変なこと吹き込むんじゃないよ、ミーア。後で僕がイザーク兄さんに半殺しにされるじゃないか」 「そもそも!そこが問題だと思うのよね、あたし」 キラの言葉に、むしろ我が意を得たりとばかりにミーアが食いつく。 しかしそこが問題と言われても、アスランには見当もつかないのだが……。 「そこ?」 「そう。アスラン、ジュール先輩とキラ以外の男の人を知らないでしょう?」 「うん」 「それじゃあ、駄目だと思うのよ。他も見てみなきゃ。ジュール先輩は確かに素敵な人だけど、兄妹でしょう?アスランはもっと、色々な人を見てみるべきだと思うわ」 ミーアの言葉に、アスランは薄く笑った。 それが真実アスランを思っての言葉だと、分かっている。 それでも、アスランは思うのだ。 きっと兄以外の人を、愛することなどないのだろう、と。 兄以上の人がいるなら、それも可能であったかもしれない。 兄以上に美しく、兄以上に賢く、兄以上に勇敢で、兄以上に情があって、兄以上に……そんな人、いる筈がない。 それが、不幸だったのかな、とアスランは思う。 アスランの世界は、兄で完結してしまった。 兄こそがアスランの理想そのものになってしまったのだ。 それでも、ああ、それでも。 兄妹。 それはなんて、重い十字架。 妹である以上、あの美しい人がそれ以上の眼で、アスランを見てくれることはない。 美しく高潔なあの人の視線に、アスランが止まることなどない。 そんな人を、愛してしまった。 そんな人に、焦がれている。 何て何てそれは、重たい十字架。 「アスラン?」 黙り込むアスランに、キラが尋ねる。 小さく微笑むと、アスランはその話を打ち切ったのだった――……。 家に一人でいるのもつまらなくて、放課後はキラと遊びに行った。 ミーアも来たがっていたのだが、今現在売れっ子の歌手に、そんな時間はない。 渋々と二人を見送るミーアと別れて、キラと一緒にゲームセンターに行って、それから一緒にご飯を食べた。 楽しくてつい時間を忘れて遊んでいた。 「あ……アスラン。そろそろ帰ったほうがいいよ」 「何で?まだ時間あるじゃない」 「もう、結構な時間じゃない。今帰らないと、10時を過ぎちゃうよ」 「兄さんはまだ帰ってこないから、一人じゃつまらないよ」 「それでも。女の子が出歩いていい時間じゃないよ。帰ろう」 キラの提案に、渋々と頷く。 町を歩いていると、軽快なポップスのメロディが聞こえてきた。 ミーアやラクスの曲以外殆ど聞くことのないアスランでも知っている、テレビでも良く流されるラブソング。 恋する女の子の切ない気持ちを、そのアーティストは歌い上げている。 でも、君はまだいいじゃないか。 歌詞の中に登場する少女に、アスランは思う。 君は、まだいいじゃないか。 気持ちを伝える術《すべ》だって、もっているじゃない。 それさえも持たないアスランにしてみれば、そんなの贅沢だ。 贅沢すぎる悩みでしか、ない。 流れるメロディを振り切るように、走った。 広大な敷地を持つジュール家の門扉《もんぴ》くぐると、誰もいないはずの家にはライトが既に点灯していた。 父さんと母さんが帰ってきたのかな、と思う。 がっしりとした造りの玄関を開けて、家の奥に向かって声をかけた。 「ただいま〜」 「アスラン!今何時だと思っている!!」 「……兄さん?」 家の奥から現れたのは、兄だった。 何故、兄が家にいるのだろう。 今日は遅くなると、言っていたのに……。 「な……なんで兄さんが家にいるの?今日、コンパだったんでしょう?」 「朝からあんなに盛大に不機嫌になられちゃ、こっちが堪ったもんじゃないだろうが。それよりも、アスラン。お前、どういうつもりだ?こんな時間までうろついて、一体何を考えている!」 「それは……」 ただ単に、拗ねていただけだ。 少しは兄も困ればいい、と。そう思っていただけ。 それなのに、こうまで怒気を露わにするなどと、彼女の想像の範疇を超えていた。 「まぁ、いい。とにかくあがれ」 促され、アスランは室内に足を踏み入れる。 リビングのテーブルの上には、ちょこんと紙袋が乗っていた。 アスランが大好きな洋菓子店の、それは紙袋だ。 「これ……兄さん、何時帰ってきたの?」 「ついさっきだ。お前ももう少しうまくやれば、俺に叱られずにすんだのにな」 「でも……」 アスランの問いに、兄はそう言って嘯《うそぶ》く。 けれど、アスランは知っていた。 その洋菓子店の営業時間は、8時までだった筈だ。 現在の時刻は、10時半になろうとしている。 兄は、待っていたのだろうか。 コンパの途中で帰ってきて、詫びのつもりでケーキを買って。 帰ってこない妹を、待っていたのだろうか。 思いついて携帯を取り出す。 マナーモードにして音を消していた携帯には、10件以上の着信がある。 全て、兄からのものだった。 「ごめん……なさい」 「何が?」 「朝のことも、ごめんなさい。我侭言って……今も、心配かけて、ごめんなさい」 ぽろぽろと、唇から言葉が溢れる。 頬には雫が伝って、それと同じくらい。 溢れて、とまらない。 最後には言葉にも出来ずに、しゃくりあげてしまった。 「いいから、アスラン」 躊躇《ためら》うように宙を彷徨《さまよ》っていた兄の手が、アスランの頭を撫でた。 もっと、もっと触れてくれていいのに。 もっともっと、触れて欲しくて堪らないのに。 それ以上の接触は、してはもらえなくて。 そこにある距離感が、二人の関係を思い知らせた。 所詮自分たち二人は、兄妹なのだ、と。 「ケーキでも食うか、アスラン。お茶を淹れてやる」 「うん」 こみ上げそうになる涙を、堪える。 それから、笑顔を作って。 何時からこんな風に、笑うようになったのだろう。 哀しくても、笑うようになったのは、何時からだっただろう。 それでも、兄を困らせたくないから。 だから、笑顔を作る。 笑顔を作って、兄に抱いている恋情に蓋をして。 兄妹。 何て何てそれは、重たい十字架。 ねぇ、僕を見て。 僕を見てよ、兄さん。 胸に響くラブソングはいつも、哀しいものばかり――……。  兄がヘタレです。 ついに妹にケーキまで貢ぐ男になりました。 頑張れ、兄。 ミーア好きが講じてミーアまで参戦です。 アスラン思いの可愛い女友達が描けたらいいな、と思います。 ここまでお読みいただき、有難うございました。 |