|
ひそやかに願うこと 密やかに……密やかに。 願う……願い続ける。 その感情はもう、狂気じみていたのかも知れない……。 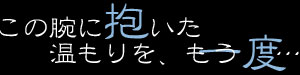 冷蔵庫に入れていたケーキを、取り出す。 妹が大好きな、イチゴのショートケーキ。 機嫌をとるために買ってきたそれを皿によそう。 紅茶を淹れたカップと一緒に妹に差し出すと、嬉しそうに微笑んだ。 「イチゴのショートケーキ……」 「好きだろ?」 「うん。有難う、兄さん。すごく嬉しい」 微笑んで、フォークを握った妹の華奢な指が、ケーキに伸びる。 口に含んで、咀嚼して。 そして嬉しそうに……本当に嬉しそうに、笑う。 「美味しい……」 「そうか」 「うん。紅茶も、すごく美味しいよ、兄さん。有難う」 「それは良かった。それにしても、よくそんな甘いものが食えるな、お前は」 呆れたように、彼は呟く。 彼自身を言うなら、彼は、甘いものは苦手だった。 物心ついて以来、好んでそんなものを口にしたことは、ない。 「女の子だもん。甘いものは、好き」 「甘いものが嫌いな女も、いると思うが?」 「いるかもしれないけど、殆どの女の子は、甘いもの好きだよ」 そう言うと、見ているだけで胸焼けを起こしそうなそれを、嬉しそうに口にする。 それでも、その笑顔が。 その笑顔が、涙が出そうになるほど愛しくて。 ただ、『兄』としての感情だけを抱ければよかった。 兄としての感情だけを抱けていたのなら、こんな物思いなど存在せず……罪悪感など抱くこともなかった。 その笑顔に触れるだけで、妹を汚しているかのような、そんな……罪悪感。 欲しいものは、目の前に在って。 目の前で、当たり前のように。 当たり前のように、微笑んでいる。 こちらの気持ちなど知りようもないからこその……だからこそ無垢なその微笑みは、時として彼を追い詰める。 この胸に抱く感情を妹が知れば、おそらく彼女はもう決して、彼に向かって微笑むことなどないだろう。 「今日は、何をしていた?」 「キラと、遊んでた」 「キラか……それなら、安心だな」 幼馴染の少年の名に、胸を撫で下ろす。 彼ならば、問題ない。 彼ならば、万に一つということもないだろう。 つい先頃まで、隣家に住んでいた、幼馴染。 そう言えば、彼にももう、長いこと会っていない気がする。 自分を慕ってくれていた、幼馴染。 「本当は、ミーアと遊ぼうと思っていたんだけど……」 「今人気の歌手を相手に、できることではないな」 「そうなんだ。今日も、仕事があるって……」 それから、妹はぽつぽつと今日あった出来事を語りだす。 それに相槌を打ちながら、二人っきりのティータイム。 「兄さんこそ、コンパはどうだったの?」 「あ?……あぁ、あまり覚えていないな」 それは、事実だった。 ずっと教授と話をしていた気がする。 それ以外では、ずっと酒を飲んでいて。 ゼミ生同士の親交を深めるためのコンパだというのに、何をしていたのだろう、と自嘲した。 「可愛い女の子とか、いたんじゃない?」 「覚えていないな」 「嘘っ!いたんでしょ?お話した?」 「ずっと酒飲んでたし……それ以外では教授と話ばかりしていた」 素直に、彼は応えた。 何だろう、これは。 まるで浮気を咎められている夫のような気さえ、してくる。 それだけきっと、妹は一人で放って置かれることに、拗ねていたに違いない。 だから、勘違いをしては、いけない。 妹は、寂しかっただけなのだから。 勘違いをしては、いけない。 自身の気持ちを、戒める。 仮令妹が彼を思ってくれていたとしても、それはあくまでも兄妹の情に過ぎない。 彼の感情と同じベクトルなど、一生描いてはくれないのだから。 飢えにも似た渇望が、ある。 この均衡を、突き崩してしまいたい、と。 時折願ってやまなくなる。 欲しいものは、目の前に在るのに。 目の前に在って、確かに微笑んでいる、というのに。 それなのに、手に入らない。 手に入れては、いけない。 そんなもどかしさに、歯噛みしながら。 自身を戒める……それは理性。 堰を切って溢れそうになる感情を戒める理性の鎖は、ともすればその苦痛さえ麻痺してしまいそうなほど、彼にとってこの苦痛は、ごく初期からの付き合いとなっていた。 大切にしたい、と思う。 妹。 愛する存在。 愛すべき、存在。 愛しくて、愛しくて堪らない。 傷つけたい、と思う。 傷つけて、踏み躙ってしまいたい。 無垢な妹だからこそ、穢してしまいたい。 処女雪の如く穢れなく美しい妹だからこそ、その無垢さが苛立ちを誘う。 この手で、穢してしまいたい。 そうすることで、妹を一生、自分のものに出来るのならば。 「兄さん?」 黙りこんでしまったイザークを不審に思ったのだろう。 妹がそう言って、イザークを呼ぶ。 それに、彼ははっと我に返った。 疲れているの、だろうか。 この、距離感に。 もどかしい距離感に疲れ果て、倦んでいるのだろうか。 突き崩せない均衡に苛立って、距離感に嘆いて。 「どうしたの?兄さん。急に黙り込んで……」 「何でもない、アスラン」 「……ひょっとしてケーキ、食べたくなった?」 「は?」 「言い出せなくて、黙ってたの?」 窺うような妹の声の調子に、彼は声を立てて笑う。 どこまでも、妹は無垢で。 だから、穢してはならない。 ……だからこそ、この手で穢してしまいたくて、堪らなくなる。 密やかに……密やかに。 願う。願い続ける。 その感情はもう、狂気を孕んでいたのかも、知れない。 その温もりを、この腕に。 抱いてしまいたくて、堪らなかった……。  『この腕に抱いた温もりを、もう一度…』をお届けいたします。 うちのイザークにしては珍しく、忍耐の人です。 まぁ、そのうち理性も灼き切れてしまうでしょう。 だって、相手はうちのイザーク。 いつまでも理性的なわけがない。 しかしこの兄妹は本当に……ここまで空回んなくてもいいんじゃないだろうか。 まぁ、空回っているのを書くのが楽しい私が、一番悪趣味なんでしょうが。 ここまでお読みいただき、有難うございました。 |