|
去年の夏の終わり いつもいつも ただ、貴方だけを見ていた――……。 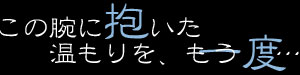 お茶をしながら、とりとめのない雑談に興じる。 兄が淹れてくれた紅茶は、絶品で。 そう言えば昔、コーヒーと同じ感覚でカップに茶葉を投入したなぁ、何て。 思わず感傷に浸る。 苦くて堪らなかっただろうに、ぴくりと眉を動かしたきり、何も言わずに兄はその紅茶を飲んでくれた。 もっとも、後で嫌味と皮肉のオンパレードだったけれど。 幼い頃のことを思い出して。 ほんの少しだけ、切なくなった。 あの頃は兄のことなんて、本当に兄として好きだと信じ込んでいた。 それは、無知だった、と。そう言うことだろうか。 時々もう、自分で自分の感情の理由が、分からなくなった。 兄が、好きで。 幼い頃から、ずっと好きで。 それはひょっとしたらただ、兄に執着しているだけなのかもしれない。 美しい兄に、執着して……自分だけのものでないことに焦れて。 予期せぬ沈黙が、辺りを包んだ。 急に、兄までも黙り込んで。 それに、慌てる。 ちょっと、沈黙が辛く感じられたのだ。 だから、話しかける。 何事もない風を、装って。 「どうしたの?兄さん。急に黙り込んで……」 「何でもない、アスラン」 「……ひょっとしてケーキ、食べたくなった?」 「は?」 「言い出せなくて、黙ってたの?」 窺うように尋ねると、兄は声を立てて笑う。 けれどどこか、それは空虚に見えて。 胸が、締め付けられる。 その理由が、知りたくて。 話してくれないことに、じれったさを感じる。 たった1歳の歳の差なのに、子ども扱いをするのは、兄の昔からの癖だった。 必要以上に子ども扱いなんて、しないで欲しい。 まるで、最初から圏外のようで、心が冷える。 少しは、意識してくれたらいいのに。 「アスラン?」 黙りこんだことに不審を覚えたのか、兄の手が伸びる。 その手が真っ直ぐと頭を撫でようとしたのが、癪に触った。 いつもいつも、子ども扱い。 そうやってアスランに二人の関係を思い知らせる、残酷な人。 いつだって兄は、彼女には優しい。 でも、その優しさは残酷だ。 少なくとも兄にはっきりとした恋情を抱いているアスランにとって、兄の優しさは残酷だった。 そんなこと、兄はきっと思いもよらないのだろうけど。 「どうした?アスラン。また機嫌が悪くなったのか?」 「……そんなことない」 小さく呟く彼女に、兄は更に小さく。 そんなことあるだろうが、と呟く。 彼女とはその髪質から違う艶やかな銀糸を、かき上げた。 その瞬間覗いたものに、声を上げる。 「どうした?アスラン」 「そのピアス……」 「あぁ、これか。どうかしたのか?」 「まだ、つけててくれてたんだ……」 「当たり前だろ」 呆然と呟く彼女に、兄は平然と答える。 その耳元には、ペリドットのピアス。 8月生まれの兄の、誕生石。 去年の夏、兄の誕生日に贈ったものだ。 「だって、他にもピアス、持ってるじゃないか」 「お前がいかに俺を見ていないか、よく分かった、アスラン」 「なっ……!そんなことないよ!」 「だったら、気づく筈だろ?俺がたいてい、このピアスをつけてることくらい」 「え……?」 告げられた言葉に、声を失った。 去年の夏に贈った、ピアス。 どうしても兄へのバースデープレゼントにしたくて、生まれて始めてアルバイトをした。 誕生日には、どうしても間に合わなくて。 贈ったのはもう、夏も終わる頃。 去年の夏の終わりに、贈ったもの。 「気に入って、くれたの……?」 8月の誕生石の、ペリドット。 兄にはどうにも似合わないような気がして不満だった。 でも、色の明度は違えど緑の宝石。 兄の身に、つけて欲しかった。 自分の瞳と、同じ色に分類される宝石。 「勿論、気に入ったさ」 震える声で尋ねると、兄ははっきりと頷いた。 それに、嬉しさが込み上げてくる。 本当は、牽制の意味合いも込めて贈ったものだったけれど。 「お前が、慣れないバイトをして贈ってくれた、俺へのバースデープレゼントだろ?」 暑い夏の盛りの、アルバイト。 何度も、日射病で倒れそうになった。 それでも、夏の間バイトを続けて。 そしてもらった給料で、贈った。 夏の終わりのあの日。 兄の誕生石のピアス。 本当は、数種類ある誕生石の中から、緑のものを選んだと言ったら、兄はどんな顔をするだろうか。 もっともっと兄に相応しいような宝石はいっぱいあったのに。どうしても、緑の宝石を贈りたかった。 そんな浅ましい内面を知ったら、軽蔑する……? 「去年の夏はそう言えば、どこにも行けなかったな……」 「うん。そうだったね」 「今年は、どこか行くか?」 「兄さん、僕受験生」 「どうせ、今の判定はAだろ?少しぐらいだったら、遊んでも大丈夫さ。その分の勉強は、俺がちゃんと教えてやるよ、アスラン=ジュール?」 去年の夏は、殆ど顔をあわせることもなかった気がする。 夏の終わりまで、アルバイト。 一度だけ、一緒に花火を見に行ったくらいだろうか。 夏の終わりの、ささやかな思い出。 確か、バースデープレゼントのお礼だった。 花火を見て、綿あめを買ってもらって。 屋台のシューティングゲームで勝負して。 ついつい対戦に白熱して、店主に商売上がったりだ、と追い出されたのを、覚えている。 「また、去年の花火大会行きたいな」 「また、あの屋台で勝負するか?」 「いつまでたっても勝負つかなくて、また追い出されるよ、兄さん」 呆れたように呟くと、兄が笑った。 どうせ、面白そうだの一言で済ませるのだろう。 楽しんでいる風な兄の顔に、思わず黙り込む。 「でも、今年は兄さん、彼女さんと行くのかな……?」 「いつまでそれを引っ張る気だ、アスラン。いないと言っているだろう」 「夏までに、出来ないとも限らないじゃないか」 「出来ないさ」 拗ねたように呟くと、兄は自信たっぷりに答えた。 いや、それはないだろ、と。心の中でツッコミをいれる。 兄ほどの、人。 周りの女の子たちが放っておくとは、思えない。 「本当かなぁ〜?」 「本当だとも」 「何で?」 「誰の告白も受ける気はないからな」 その言葉は、他の人間が聞けば傲慢、と。そう取るかもしれない。 それでも、彼女は兄の言葉が嬉しかった。 暫く、兄が自分だけのものであってくれるような錯覚を覚えて、嬉しかったのだ。 「綿あめ、買ってくれる?」 「いいぞ」 「りんご飴も、食べたい」 嬉しくて、甘えてみる。 兄が笑ってくれて、余計に幸せな気持ちになった。 そんな気持ちで贈った、去年の夏の日。 我侭な独占欲。 ペリドットの、ピアス。  『この腕に抱いた温もりを、もう一度…』をお届けいたします。 何やら、青い風が吹いているような気がする今日この頃です。 何、これ。 本当に兄妹モノ?とか言われそう。 た……たまには幸せもいいんじゃないですかね。 もうすぐ、兄の理性も切れますし。 たまには……ね? ここまでお読みいただき、有難うございました。 |