|
「親友」 それは祈りにも似た渇望であり 嫉妬にも似た 願い――…… 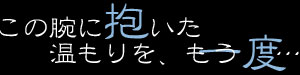 大学からの帰り道、バイクを飛ばして家路を急ぐ。 折り悪く引っかかった赤信号に舌打ちすると、じぃっと自分を見つめる視線に気づいた。 昨年まで身に着けていた制服に、褐色の髪。紫雷の瞳を持つ少年は、所謂『幼馴染』だった。 「キラ?」 「やっぱり、イザーク兄さん」 路肩に寄せてメットを外すと、ほっとしたように相手は溜息を吐いた。 優秀な人間であるというのに、気の弱いところは相変わらずらしい。 「今日は、高校早かったんだな」 「うん。テスト期間中だから。イザーク兄さんは、大学の帰り?」 「そんなところだ。……うちによって行くか?」 「う〜ん、どうしようかなぁ……」 彼の言葉に、キラは考える素振りを見せる。 どちらにしろ、気持ちが傾いているのは見ているだけで分かった。 毎度毎度、テスト期間中は騒動が持ち上がるのが、ジュール家の慣例だ。その震源地が、たいていこの幼馴染であることも、言うまでもない。 「……勉強見てやってもいいぞ」 「ほんと!?いやぁ、いつも悪いねぇ、イザーク兄さん」 悪びれた様子もなくいうと、ガードレールを飛び越えて車道に侵入してきた。 予備のメットを渡すと、それを被り、荷台に腰掛ける。 大事そうに鞄を抱えているが、どうせその鞄は殆ど空だろう、と彼は見当をつけた。 それも、いつものことなのだ。 「おい、準備はいいか?」 「いつでもいいよ」 キラの言葉を受けて、彼はウィンカーを上げた。 そのまま一息に、自宅を目指してバイクを走らせた――……。 ジュール家の邸宅に辿りつき、バイクを止めると、ふらふらとキラは荷台から降りた。 足元は、だいぶ覚束ない。 吐かないだけマシだが、地面にへたり込んでしまった。 「おい、キラどうした?気分が悪いんだったら、何で帰るって言わなかった」 「違う、イザーク兄さん……兄さん、スピード出しすぎ」 「そうか?」 顔面蒼白の状態で言い募られても、彼自身の感覚ではスピードを出しすぎた、ということはない。 思わず怪訝な顔をすれば、幼馴染の少年は恨めしげに彼を凝視した。 「そうか?じゃないよ。イザーク兄さん、本当に免許持ってるの?道交法って知ってる?制限速度って知ってる?」 「知っているとも。当たり前だろ?」 「じゃあ、何で守らないのさ!」 耳を劈くような鋭い声に、彼は顰めっ面をした。 その表情から推し量るに、腹に抱えた言葉は「それがどうした」あたりが適切だろうか。 「別に、危険な運転をした覚えはないが?」 「十分危険だよ!時速何キロで走っているのさ!」 「……80キロ?」 「何で疑問系……じゃなくて!制限速度は50キロ!」 「小姑みたいだぞ、キラ」 なおも言葉を紡ごうとするキラに、彼はきわめてあっけらかんと答えた。 さすがに怒気を殺がれたのか、キラは肩で小さく溜息を吐く。 「……もう少し、道交法は守ってよね。イザーク兄さんがスピード狂って言うのは、見たまんまって言うか、そのまんまって言うか、納得って言うか、だけど」 「……言ってくれるじゃないか、キラ。しかし、一言言わせてもらうとするなら、俺よりアスランの方がずっと、スピード狂だぞ」 「……イザーク兄さん。寝言は寝てから言った方がいいよ」 彼の言葉に、キラはやれやれ、と。溜息さえ吐いてばっさりと切り捨てた。 客観的に外見上の問題を考慮すると、どう見てもおとなしやかなアスランが、彼以上にスピード狂とは、見えないということだろう。 「寝言じゃない、真実だ。この前だって、後ろに乗りながら大はしゃぎの上、もっとスピード出ないの?なんてほざいたぞ?」 「嘘……」 彼の言葉に、少年は呆然と呟いた。 否、この場合は『絶句』の方が適切だったかもしれない。 「アスラン、暴走車に乗り合わせたら停学って校則、知らないのかな……」 「おい、何が暴走車だ、何が」 「暴走車じゃないか!制限速度30キロもオーバーしてたら、立派に暴走車だよ!」 きゃんきゃんと噛み付いてくる幼馴染の少年に、耳を塞ぐジェスチャーで応える。 少年の小言は右から左だ、と。そういうことだ。 余談だが、彼の妹であるアスラン=ジュールは、制服姿で彼のバイクに乗り合わせること多数である。 「あれ……?兄さんにキラ。どうしたんだ?」 「ただいま、アスラン。大学帰りに、鉢合わせてな。拾ってきた」 「拾っ……!ちょっと、イザーク兄さん!僕は捨て犬でも捨て猫でもないよ!」 「そうだな。犬猫の類じゃないな。小動物系でないことは確かだ」 「……兄さん。僕に喧嘩売ってるでしょ」 買うよ?と言いたげに、少年は黒い笑みを浮かべた。 確かにこの様子を見てみれば、犬猫系の……所謂小動物系に当て嵌まらないのは、自明の理と言えるかもしれない。 「で?何で、キラがうちに来てるわけ?」 「イザーク兄さんが、勉強教えてくれるって言うんだもん。僕ほら、文系はさっぱりじゃない?アスランに教えてもらおうにも、アスランも文系は苦手だしね〜」 「ずるい、兄さん!僕にはあまり教えてくれないのに、何でキラの勉強は見てやるんだよ!」 「あ〜、分かった分かった。お前のもちゃんと見るから。制服着替えてリビングに来い」 腹の中では、お前にも教えているじゃないか、と呟きながらも、彼はあっさりと答えた。 面と向かって一対一で接するのはやはり、躊躇いを覚えるけれど。 間に幼馴染の少年を挟めば、それも解消されるだろう。 幼い頃から、彼ら三人――幼馴染は、もう一人いるので四人、ということになるのだが――一は、ともに育ってきたようなものなのだから。 少年をリビングに通すと、人数分の紅茶を淹れる。 お茶請けには確か、クッキーがあった筈だ。彼自身は甘いものは好まないが、彼の妹と少年は、甘党だ。何か、甘いものを用意してやった方がいいだろう。 幸い、妹が甘党と言うこともあって、メイドの手で常に、菓子類は常備されている。 「紅茶じゃなくて、ジュースはないの?イザーク兄さん」 「ジュース?」 「そ。コーラとか、ペプシとか。スプライトでもいいや。ない?」 「そういう類は誰も飲まないからな……100%オレンジジュースならあるぞ?」 「……子供じゃないんだからさ、兄さん」 ぶーたれて、少年は答えた。 この分だと、クッキーよりポテトチップス、とでもいいそうだ。 しかし彼の家には基本的に、ジャンクフードの類は置いていないのだ。炭酸飲料なんて論外といえる。 「何度も言うが、キラ。この家には炭酸飲料の類なんて置いてないぞ」 「何度も言うけど、ジュースぐらいはあった方がいいよ」 「紅茶とコーヒーで十分だ」 「それって兄さん、絶対におかしいよ。若いんだから、ジュースぐらい飲みなよ」 やれやれ、と言いたげに首を傾げる幼馴染をドツキたいと思ってしまってもそれは、仕方がないだろう。 とりあえず彼はシカトして、さっさと紅茶とお茶請けの用意をした。 ややもすると、自室から大量の教科書とノート、それに辞書を抱えて妹が降りてきた。 服装は、大きく襟ぐりの開いた七部袖のカーデの下に、ペールブルーのたっぷりとしたレースで縁取られたキャミソール。 それにジーンズの組み合わせだ。 「お茶の準備くらい、僕がするのに、兄さん」 「アスラン、僕はジュースが飲みたい」 「だったら自分で買って来い、キラ。確か近所に、ベンディングマシーンはあった筈だぞ」 「アスラン……冷たい」 ヨヨヨ、と涙を拭う素振りを見せながら、キラは言う。 彼以上にキラを良く見知っている妹は、既にそれを黙殺して、さっさと席に着いた。 くっと紅茶を湛えたティーカップを傾けて啜ると、馥郁《ふくいく》とした芳香が口内に広がる。 妹は、満足そうに溜息を吐いた。 「ん。美味しい。……味音痴のキラにまでこの紅茶を振舞うのは勿体無いよ、兄さん」 「ちょっ……!味音痴って何さ、味音痴って!」 「あぁ、すまない、キラ。味音痴は、言いすぎだったようだ。そうだな『大人の味覚が分からない』と言うことにしておこう」 ふふん、と笑って。妹は、そう言った。 二人の間に漂うのは、『親友』ならではの気安い雰囲気。 そこに存在する『絆』に、妬心を覚えるのは、致し方ないことなのかもしれない。 どうあってもそれは、彼が手にすることの叶わぬもの、だから。 兄と妹。誰よりも、強い絆で結ばれている。 その身に流れる血は、多少の違いはあっても、同質のものだ。 断ちがたい絆で、確かに結ばれているというのに。 その『絆』が、時折無性に重いものに感じられる。 その『絆』こそが、何よりの罰であるかのように。 兄と、妹。 こんなにも愛しているのに、決してそれ以上の感情で相手を見てはいけない、と。戒めるこの『絆』こそが。 重たくて、仕方がなかった。 だからこそ、羨ましいものに感じられて、しまうのだ。 『親友』。 その『絆』は彼では決して届かないものであり。 彼が抱く罪悪を、免罪してくれるような色さえ帯びているから。 「もう、イザーク兄さん!少しはアスランを窘めてよ!」 「あ……あぁ」 「……?どうしたの、兄さん」 憤慨するキラの言葉に、うっかり呆けた答えをしてしまった。 大きな翡翠の瞳を瞬かせて、そんな彼に妹が問いを重ねた。 吸い込まれてしまいそうなほど、煌く一対の翡翠。 華のような顔《かんばせ》を支える頸は、容易に縊り殺せそうなほど、細くて。 その衝動は、喉が渇いてしまうほどの魅惑的な香りさえ、振りまいているから。 「親友」 自分では、決して届かないもの。 「他人」にカテゴライズされるものが、羨ましくて仕方がなかった。 どうあっても、それは届かないものだから。 どうあっても、彼と妹が兄妹であることに変わりは、ないから。 「どうもしていないさ、アスラン。……ほら、どこが分からないんだ、二人とも」 「そう……?」 彼の言葉を、完全に納得していないのだろう妹が、訝しむように彼を見上げる。 それに、淡く笑うことしか、できなかった――……。 絶対的なものが この身を苛むものなのだと したら そんなものは 要らなかった いっそ『他人』にカテゴライズされる『絆』だったら 良かったのに――……  キラに対して全く嫉妬なんてしていないっぽい兄ですが。 妹と『他人である』ということだけで十分、嫉妬の対象にはなるようです。 「親友」というお題に対して、『他人にカテゴライズされるもの』という風な解釈はちょっと、飛躍しすぎかな、とも思うのですが。 血縁者だからこその罪があるならば、他人だからこその赦しも、あると思うのです。 どうにもこうにも、言葉足らずの感は、否めないのですが。 ここまでお読みいただきまして、有難うございました。 |