|
嗚呼 どうか泣かないで 泣かないで キミの哀しみを ボクは知っている だからどうか 泣かないで どうか一人で 泣かないで キミの嘆きを 理解できるのは ボクだけなのだから――……。  第Ⅰ章-04- くすり、と。ギルバート=デュランダルは、意味ありげに微笑んだ。 それはまさに、人間を堕落へ誘う悪魔の、甘言に似ていた。 言葉は、甘く。けれどどこか、苦い。 しかし、それはまさに『アスラン』が、望むものだった。 『アスラン』が望み、『アレックス』が渇望してやまないもの。ただ一人の、『対の遺伝子』であり。そして恋してやまない青年。 どろりとした闇を宿す翡翠の瞳が、熱っぽく煌いた。 「君の持ってきた情報に対し、私は君のプラント市民権を回復すると言う代価を払おう。そして……」 「議長……」 「そして、君のザフト復隊に対しては、特務隊FAITHへの叙任、新型MSの授与、そして……」 そこで、デュランダルは徐に言葉を区切った。 その先を期待して、けれどどこか諦めたように。次の言葉を、美しい翡翠が待つ。 その瞳は、もうデュランダルを殆ど映してはいなかった。彼女の瞳に、確かにデュランダルの姿は、映っているのだけれど。彼女の脳裏に存在するであろう意識の鏡に、デュランダルの姿は映し出されていない。 彼女はデュランダルを素通りして、ただ一人を一身に追いかけていた。 「君の『対の遺伝子』を、君に還そう。……プラント市民としてね」 「……馬鹿なことを」 けれど、デュランダルの言葉を、アスランは切り捨てる。 そんなことは、ありえない。 すぐそこに、恋してやまない青年の姿が、ある。 議長の御前だからだろう。礼儀を守って、先ほどから一言も彼は、言葉を発していないけれど。それでも、強く強く煌く一対の蒼氷は、彼女を真っ直ぐと射抜いて縛り付ける。 彼は、驚いているけれど。 けれど同じだけ、感情を素直に吐露していた。 還ってこい、と。そう言われている気が、して。 求められている、その事実が嬉しく愛しい。 けれど、有得ない。 彼女の中の冷静な部分が、そう判断する。 そんなことは、有得ない。 『対の遺伝子』それは、プラントに存在する夢の形。幻想の象徴。 彼の『対の遺伝子』は、実際には確かに『アスラン』だったけれど。けれど、彼が『対の遺伝子』と謳われた相手は、『アスラン』ではなかった。 笑えないほど滑稽な喜劇だけれど。『アスラン』と彼は、『対の遺伝子』でありながら、『対の遺伝子』と。プラント市民に明かされることは、なかった。 「確かに、私とイザークは、『対の遺伝子』です。生まれながらの、遺伝子の片翼と。生まれながらに私たちは一対なのだ、と。父もエザリア様も仰っておられた。でも……でもイザークの婚約者は、ラクスだ」 「そう、だね。しかし……」 「議長。僭越ですが、そこから先は私が直接、彼女に話します。暫し、お時間をいただけないでしょうか」 「あぁ、構わないよ、ジュール隊長。それならば私は、席を外そう」 「いえ、我ら両名が席を外します。そして後ほど、またこちらに参上いたします」 彼、の言葉に。デュランダルは鷹揚に頷く。 静かな口元には、うっすらと笑みの片鱗さえ、刷いて。 デュランダルが頷いたのを確認して、彼は『アスラン』の元へやってきた。 手を、差し出して。彼女の腕を、掴む。 その瞬間湧き上がったものは、紛れもない歓喜だった。 「行くぞ、アレク」 「ぁ……うん」 「では、議長。また、後ほど」 一礼して、彼は議長の前から、『アスラン』を連れ出した――……。 「イ……イザーク!」 「何だ?」 「その……今回のプラント訪問は、極秘だから。人目に付きたく、ない」 「……第一声がそれか、貴様は。……心配しなくても、人目に付く恐れのないところだ」 「そ……そっか」 腕を引かれながら。けれど彼女は、混乱していた。 先ほどの議長の言葉。その真意が、分からない。 イザークは、モノじゃない。 幾ら『還す』と言われても、モノの受け渡しではないのだから、そう上手くいくとは思えない。まして、イザークには既に、定められた相手がいる。それを放棄することは、果たして可能なのだろうか。 ……やはり、可能とは思えなかった。 今、プラントにラクス=クラインはいない。定められた相手として、彼が隣に立つべき少女は、いない。 幾ら彼がその婚約を無効と訴えても、プラント市民がそれを受け入れるとは、思えない。 それだけの、幻想なのだ。『対の遺伝子』といい『定められた相手』と謳われる、その幻想は。 そして彼はその幻想の、片翼を担う、者。 プラントに生きる、幻想を。その夢の形を、彼は紡ぐ立場に、在るのだ。 ラクス=クラインはもう、プラントにいなくて。彼女はその隣に、イザークではない男を侍《はべ》らせているけれど。それでもそれが、プラントを支配する、夢の形。 一般の、善良なプラント市民はまだ、その夢を信じている。その幻想を、生きている。 その幻想を自ら生み出したクライン派と、その幻想の終焉を垣間見たザフトの中では、もう死んでしまった幻想だけれど。 彼の歩みが、止まった。 つれてこられた場所は、プラント――評議会が構えられているアプリリウス・ワン――を一望できる、展望室の最上階だった。 眼下に広がるのは、空気のない真空の宇宙で、這いずるように懸命に生活の場を開拓し、生活を営んできたコーディネイターたちの、その努力の結晶だ。 「……キレイ」 「先の大戦でかなりの打撃を被ったが、プラントも、ここまで復興した」 「そうか……良かった」 「見せてやりたかった。貴様は、戦争の爪痕を深く残し、悲嘆に暮れるプラントを見たのが、最後だっただろうから」 「うん……有難う」 嗚呼、駄目だ。 彼にあったら、言いたいことがたくさんあった。『アスラン』ではなく、『アレックス』を見て欲しくて。自分のものに、したくて。 言いたいことも、色々あったのに。 眼下に広がる景色と、穏やかなその顔に、何を言いたいのか、忘れてしまう。 「アレク……いや、もう、偽名を言う必要はないか。ここには、誰もいないから」 「……俺が、『アスラン』として此処にいるならば、そうだろうね」 「どういう意味だ?」 「俺が、プラントの『アスラン=ザラ』として此処に立っているか、オーブの『アレックス=ディノ』として此処に立っているかで、俺を意味する名前は変わるんじゃないか、って。そう言うことだよ」 にこり、と。『アレックス』は笑う。 その笑顔は、どこまでも麗しく。けれどどこか、毒のある。議長の前で見せた、独特の笑みを、浮かべて。 そんな彼女に、イザークは苛立たしそうに舌打ちをした。 「君は……どっちの俺に、此処に立って欲しいのかな……?」 囁きながら、彼の首にその腕を回す。 深く深く。彼の吐息を飲み込むように、顔を近付けて。唇が触れ合いそうなほど……吐息が感じられるほど、顔を寄せ合って。 深く鮮やかな翡翠の瞳を見せ付けるように。彼の蒼氷の瞳を、覗き込む。 苛立たしげに眉を寄せながら、それでも彼の片手が、『アスラン』の腰に回された。 口付けを乞うように、『アレックス』は伸び上がる。 しかし唇と唇とが触れ合うよりも早く、彼のもう片方の手が、『アスラン』の後頭部を抑え。そのまま、荒々しい仕草で唇を塞いだ。 「っん……」 不意をつかれて、言葉を飲み込んだ。 要らない言葉を吐くアスランの唇を、塞ぐ。近すぎて見えない、深く深くどこまでも鮮やかな翡翠はきっと、驚いて見開かれているのだろう。 それを思うと、少し愉快だった。 彼にとって要らない言葉ばかりを吐くのなら、呼吸なんて止めてしまえば、いい。 触れ合うだけの口付けでは満足できず、その唇に舌を這わせる。 毒を吐くくせに、その唇は酷く、甘く。微かに洩れる、その吐息さえも甘くて。 微かに開かれた甘い唇の、その狭間から侵入し、思うさま貪る。 蜜が溢れて、白い『アスラン』の頬を、濡らした。 漸く解放すると、『アスラン』はぐったりとイザークに凭れかかる。 さすがに、久々だと言うのに無茶をしたかと一瞬青褪めたが、すぐにその心配は杞憂であることを、悟った。『アスラン』はイザークの胸に凭れながら、肩を震わせていた。――笑っているのだ。 「誰かに見られたら大変だ、イザーク。君は、『ラクス様の婚約者』なんだから」 「だから、それは!」 「ねぇ、イザーク」 不意に、『アスラン』の笑い声がやんだ。 笑みに崩れていた、花のように麗しい顔《かんばせ》を、今度は皮肉に歪める。 翡翠の瞳に、冷たい光を、宿して。 「ねぇ、イザーク。信じられると思うのか?」 「……アスラン」 「どれだけ、どれだけ嘆いたと思う?ある日突然、俺の『遺伝子の片翼』であり、『生まれながらに一対』であった君が、君と、ある日いきなり、そうではなくなった。ある日いきなり、俺の片翼であった人は、他の少女と一対と謳われた。ねぇ、イザーク。俺が、どれだけ嘆いたと思う?」 俺たちが、どれだけ嘆いたと思う? 言葉にはしないけれど、『アレックス』はそう思った。 どれだけ嘆いたというのだろう。その嘆きが、彼に分かるだろうか。 母を喪い、対の存在を奪われた。その苦しみが、分かるだろうか。――分かるわけがない! 嘆いた、嘆いたよ。『二人』で。 その喪失を、嘆いた。どうして、どうして、と。 刷り込み出会ったのかもしれないけれど、『アスラン』も『アレックス』も、対の存在である彼を、彼に、恋した。 刷り込みだったのかも知れないけれど。だからこそ、より強く。誰よりも強く、恋したのに。 それなのにその存在は、一度離れた――引き離された。 その嘆きを、痛みを。思い返すことは、こんなにも容易い! 「イザーク、イザーク、イザーク。君に、分かるわけがない」 「……そうだな」 確かに、イザークには分からない。 『アスラン』が味わったとか言う絶望は、イザークのものではなく。その嘆きも痛みも、イザークのものではなく。 『アスラン』を襲った悲しみは『アスラン』のもので。理解したいと思っても、それは真実理解したことにはなりえない。仮に理解できたとしてもそれは所詮そう『認識』するだけの話で。そう『実感』するわけでは、ないのだから。 『アスラン』の苦しみは、『アスラン』だけのもので。『アスラン』の嘆きは、痛みは『アスラン』だけのもので。それは決して、真実理解できるものではなくて。そんなことは、分かっているから。 「話を聞くよ、イザーク」 「……アスラン」 「君の言い分を聞く。それから、俺はさっきの質問に答える。それでいいだろ?」 つん、と顔を上げて、『アスラン』は言った。 どこか、イザークはその様子に違和感を感じる。 彼の知る『アスラン』とはちょっと、様子が違っているように、感じられたから。 けれどささやかな違和感はすぐに、霧散した。2年。2年だ。 二人が離れてからもうすぐ、2年になる。それは、決して短いとはいえない月日が、二人の間に流れているのだ。印象が変わってしまうのも、当たり前ではないか。 溜息を飲み込んで、イザークは静かに口を開いた。 「ラクス=クラインと俺の婚約を貴様が言っているのならば、それはとうに破棄されている――破棄した」 「出来るわけがない」 「……出来た。したんだ。今、プラント国民の誰一人、俺とラクス=クラインが婚約者だと信じているものはいない」 「どうしてそれができたって言うんだよ。ラクスは、オーブにいるんだ。ラクス=クラインが表に出ず、お前の言葉だけで、プラント国民の何人が、お前の言葉を信じると思う?」 「確かにな」 『アスラン』の言葉に、イザークは静かに頷いた。 確かに、そうだ。その通りだ。 人々の中に息づくのは、『ラクス=クライン』と言う平和の象徴、聖女の幻想で在って。彼女の『対の遺伝子』と言うものも、周りの人間にしてみれば、彼女に付属するオプションに過ぎない。 ラクス=クラインの付属物にしか過ぎない彼女の婚約者であるイザーク=ジュールの言葉を、プラント国民の何人が信じると言うのだろう。 答えは、簡単だ。簡単に求められてしまう解答。初級の数学よりも、簡単に。 答えは、ゼロに等しい。それだけだ。 「例えば貴様がラクス=クラインと婚約して、それで今、その婚約はとうに破棄されていると言っても、誰も信じないだろう。貴様は三隻同盟の一員として、ラクス=クラインとともに戦っている。でも、アスラン。俺は、違う」 「イザーク」 「俺は、婚約者が『平和のために』プラントと戦うことを誓ったとき、『プラントのために』彼女と戦った側の人間だ。あの女を神聖視し、崇める立場の人間からすれば、赦し難い背信行為だ」 彼らの信奉する聖女への、裏切り行為にも等しい。 イザークはそう言う。 けれど、『アスラン』には、そうは思えない。 プラントで今もなお生きている『ラクス=クライン』と言う名の幻想。その幻想が生きている以上、ラクスの行為は、プラント国民にとっても、英雄的所業として語り継がれているのではないだろうか。 ラクス様がプラントのために戦ったのと同様に。その婚約者であるイザーク=ジュールもまた、プラントのために戦ったのだ、と。そう言う幻を見て、その幻を愛しているのではないのか。 それが、ラクス=クラインと言う聖女の、幻想だ。いつでもプラントを愛し、プラントを慈しみ、プラントのために歌う。それが、ラクス=クラインの幻想。 その幻想は途切れることなく、今もなお語り継がれている。 心地よい、その夢。その幻想。 「戦時中に、まず俺の方からクライン派へ申し入れた。ラクス=クラインが国家反逆罪でプラント中を追われているときだ。ザラ前議長の口ぞえもあった。まぁ、かなり反感を買った挙句、裏切るつもりかと連中からは罵られたが、その時は、ザラ派の母を持つ俺の立場は、結構強かったからな」 「へぇ……」 「戦後、今度は俺が断頭台へ送られそうになった。その時、今度はクライン派から言われたさ。ラクス=クラインに、俺は相応しくない婚約者なのだ、と。今度はクライン派から破棄が宣告された。まぁ、ラクス=クラインの体面を慮ってか、公にはされなかったな。『プラントのために』戦った婚約者を、戦局が定まってから見捨てたのでは、彼女の伝説に傷がつくとでも考えたのだろう」 「そんな……」 「そして、今回。公に、俺たちの婚約の破棄を、訴えた……方法は、今は明かせない。でも、公的にも、俺とラクス=クラインの婚約は、破棄されている」 「それを、信じろと?」 「俺には、そうとしか言えない」 信じろ、と言われれば。信じたいとしか、『アスラン』には、『アレックス』には、答えられない。 それは、『彼女』が。『彼女たち』が、何よりも望んでいたこと。 その望みを、こんな形で与えられて。どうしていいのか、『アレックス』には、分からなかった。 何ともしようのないことだな、と。『アレックス』は溜息を吐く。 『あいつ』だったら、どんな反応を返すだろう。あの『アスラン』だったら、どんな反応を。イザークに、返すだろうか。 イザークの望む返答を、『アスラン』ならば返せたのだろうか。自分のように、困ることなく。 だって、なんと返せばいいのか、分からない。 嬉しい、嬉しい、嬉しい。 彼に婚約者がいないならば、それは本当に嬉しい。それが、『アレックス』の本心だ。本当に本当に恋してやまない相手だから。その相手が、今フリーであるという事実は、掛け値なしに嬉しい。 でも、『アスラン』はそう言うだろうか。 『アスラン』ならば、嬉しいとは言わない気が、する。周囲に気を遣いすぎるほどに気を遣って、自分の身を食い殺すタイプの人間だ、『アスラン』は。 イザークだって、それは知っているだろう。だから、ここで『アレックス』が嬉しいと言えば、違和感を感じるに決まっている。 『アスラン』ならば、どう答えるだろう。 『アスラン』ならば、イザークに何と言って答えるだろう。 苛々としながら、『アレックス』は思う。 『アスラン』よりも『アレックス』はずっと、その精神が幼かった。『アスラン』の時間よりも彼女の彼女としての時間は、ずっと少なかったから。 「だから、戻ってこい、『アスラン』」 もう一度、帰ってこい。 プラントに、此処に。 帰ってこい、『アスラン=ザラ』と。イザークが、言う。 帰って来い アスラン=ザラ 俺の元に 帰っておいで 真摯な蒼氷に。 『アレックス』は釣り込まれるように、頷いていた――……。 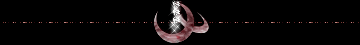 『白い闇』第4話をお届けします。 ほら、勝手設定のオンパレード《笑》。 いえ、ここからが本番なのですが。 お付き合いいただけましたら、幸いです。 ここまでお読みいただき、有難うございました。 |